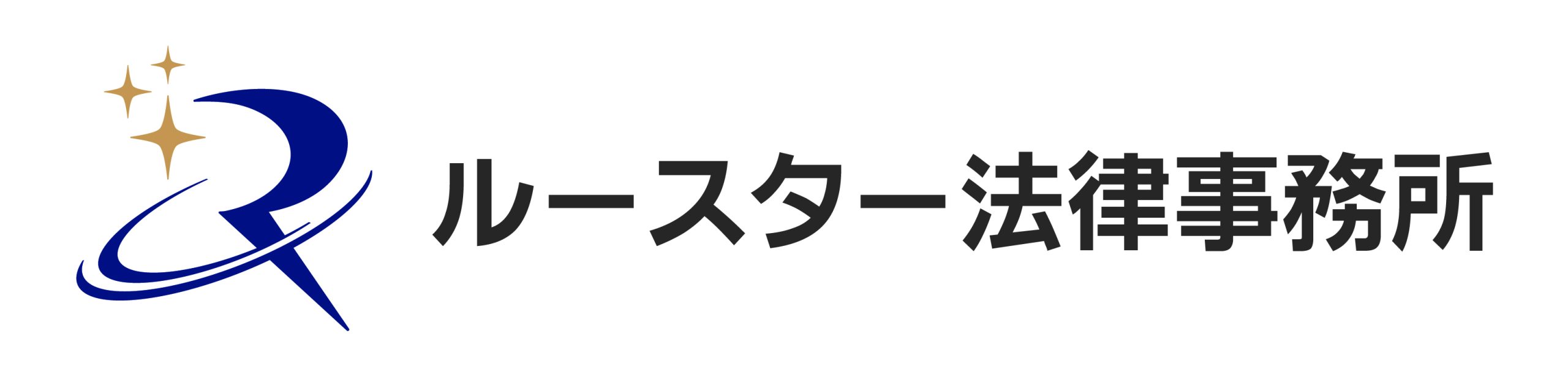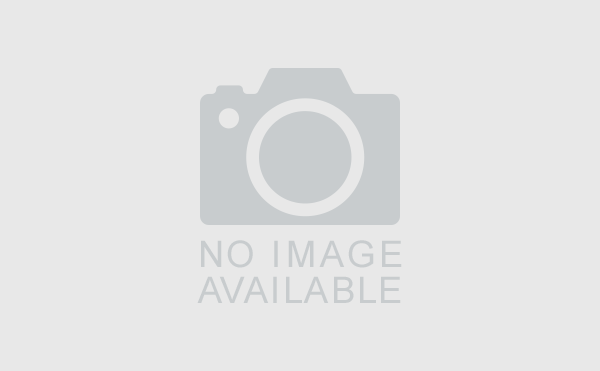「PR業務委託契約書」のポイントとひな型を解説
こんにちは。ルースター法律事務所 代表弁護士の山本です。
プロモーション活動の一つとして、インフルエンサーに自社商品やサービスの紹介を依頼するという方法があります。
「インフルエンサーマーケティング」や「企業案件」などとも呼ばれ、近年、こういったマーケティング手法を活用するケースはますます増えているように感じます。
しかし、PRを依頼するにあたっては、どの程度の期間PR投稿を公開するか、公開されたコンテンツの二次的利用はどこまで可能かなど、予め決めておかないと後々トラブルにつながりかねない事項が多々あります。
また、インフルエンサーが競合他社の商品・サービスのPRに出演することを容認するか否か、インフルエンサーによる違法行為や不祥事が発覚した場合はどのように処理すべきかと言った点については、特に重大なトラブルに発展する可能性があり、慎重に契約条項を作成する必要があります。
そこで今回は、トラブルを防ぐために重要となる「PR業務委託契約書」のポイントと、それを踏まえた条項例を解説していきたいと思います。
PR業務委託契約とは
PR業務委託契約とは、企業(広告主)が自社や自社商品・サービスの広告・宣伝を目的として、インフルエンサー(代理店や事務所を含む)に対してPR業務を依頼し、その見返りとして報酬を支払うことを内容とする契約を言います。
本記事では便宜上「PR業務委託契約書」としていますが、「インフルエンサー業務委託契約書」や「宣伝委託契約書」など、これと異なる名称が用いられたり、単に「業務委託契約書」のタイトルで締結される場合もあります。本記事では、上記のような【PRの依頼 ⇔ 報酬】という要素を持つ契約をすべて「PR業務委託契約書」と定義します。
PR業務委託契約のポイント
上記の通り、広告主がインフルエンサーに対して依頼するPR業務と、その対価として支払われる報酬がPR業務委託契約書における本質的要素となります。
したがって、①PR業務の具体的内容と、それに対する②報酬を明確にすることが出発点となります。
また、③制作されたコンテンツの権利帰属や、二次的利用の範囲なども明確にしておく必要があります。
加えて、トラブルに発展しやすいポイントとして、④インフルエンサーによる競合商品・サービスのPR出演の可否(競業避止義務)に関する事項や、⑤インフルエンサーによる不祥事等が発覚した場合の措置についても規定しておけば、いざという時にもスムーズに対応可能な契約書にすることができます。
以下、上記の5つのポイントを中心に、PR業務委託契約書のポイントと条項例を解説していきます。
① PR業務の詳細(コンテンツ、内容、期間など)に関する定め
インフルエンサーが具体的にどのようなPRを実施するのかを明確にすることが、PR業務委託契約を巡るトラブルを予防するために最重要の事項です。
おそらくもっとも典型的なケースは、PR動画などのコンテンツの制作・配信の依頼かと思われます。
つまり、1)インフルエンサーが広告主の商品・サービスを紹介する動画などのコンテンツを制作し、2)制作した動画をインフルエンサーのYoutube、インスタグラム、TikTok等のアカウントにて配信する、といった内容です。
以下、PR動画の制作・配信を依頼するケースを想定し、契約書で定めておくべき事項とそのポイントを解説していきます。
コンテンツ(PR動画)の制作に関する事項
動画制作については、①PR動画の尺・本数、②PR動画の出演者、③制作の納期、④具体的な企画、構成、内容、⑤制作された動画の納品・修正などが決定すべき事項として挙げられます。
このうち、①動画の尺や本数、②出演者、③納期といった客観的な事項は、報酬の算定の基準・目安とされることも多く、事前に明確に定めておきたいところです。
他方、④動画の企画や構成、内容といった部分は、契約締結段階では明確に決まっていないというケースも少なくないでしょう。むしろ、インフルエンサーの自由な企画力に期待して、あえて縛りを設けたくないと考えることもあるかと思われます。
とはいえ、あまりにイメージと違う内容になってしまうことは避けたいところです。
そこで、PR動画の企画、構成、内容等については、都度双方の協議により決定し、その内容に従って制作を行う、といった定め方にしておくのが無難でしょう。
また、⑤完成したPR動画の納品方法や、確認・修正のフローについても定めておく必要があります。
特に、インフルエンサー側にしてみれば、撮影のやり直しが生じたり、何度も編集や修正を行ったりすると、報酬額と見合わなくなってしまう可能性があります。
そこで、修正の範囲や回数などについて、可能な限り明確に定めておくことが望ましいと言えます。
コンテンツ(PR動画)の公開・配信に関する事項
PR動画の公開・配信については、①配信媒体、②配信期間などが重要な決定事項となります。
特に、PR動画をどのアカウントで、どのくらいの期間にわたって公開するかは双方にとって重要なポイントとなりますので、しっかりと明記しておくことが必要です。
条項例
以下、上記のPR動画の制作・公開に関する事項を定める条項例を紹介します。
詳細は別紙にて定めることとし、別紙の記載例もあわせて掲載していますので、これを参考に適宜アレンジして利用して頂ければ幸いです。
第X条(契約の目的)
広告主は、インフルエンサーに対し、別紙業務明細書で指定する広告主の商品(以下「本商品」という。)のPRを目的として、本商品を紹介する動画の制作及び配信業務(以下「本件業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。第X条(委託内容)
本件業務の内容は、次の各号に定める業務とする。
(1) 別紙業務明細書で指定するYoutubeチャンネルその他の受託者が運営するSNSアカウント(以下「本チャンネル等」という。)上における、本商品等を紹介するPR動画の配信(以下「本配信」という。)
(2) 別紙業務明細書に定める内容、仕様等に基づいて、本配信の対象となる動画及び本配信に関連するグラフィック、文書、音声その他のコンテンツ(以下「本コンテンツ」という。)の制作を行う業務
(3) その他前記各号に附帯関連する業務第X条(本コンテンツの制作・修正)
1. インフルエンサーは、別紙業務明細書で定める期日までに本コンテンツを制作し、広告主に納入する。
2. 広告主は、本コンテンツの納入を受けた後、別紙業務明細書に定める期間(以下「検査期間」という。)までに、本コンテンツに所定の仕様等との不適合がないかを検査する。検査に合格したときは、インフルエンサーに対して検査合格の通知を行い、これをもって検収完了とする。
3. 検査の結果、本コンテンツが不合格となった場合、広告主は、インフルエンサーに対して遅滞なく具体的理由を付したうえで不合格の通知を行う。この場合、インフルエンサーは、双方協議の上定めた期間内に、別紙業務明細書に定める範囲内にて、自己の費用と責任において不合格の原因となった不適合を修正または削除し、再度検査を受けるものとする。
4. 検査期間内に、前項の不合格通知が交付されなかった場合には、検査期間の経過をもって、本コンテンツは検査に合格したものとみなす。第X条(本配信)
本配信について、公開日から別紙業務明細書で定める期間を公開保証期間とし、インフルエンサーは当該期間は削除をしてはならない。なお、当該期間経過後もインフルエンサーは本配信を公開し続けるよう努めるものとするが、本配信の公開に関して何らの責任を負うものではないものとする。
別紙記載例
| 対象商品 | ●●● |
| 配信媒体 | 媒体:Youtube アカウント名:●●●チャンネル |
| コンテンツの仕様 | 出演者:●●● 概要:本商品のPR動画 仕様:1) ●分程度の尺の動画1本及び当該動画を切抜編集したショート動画●本 2) 企画、構成等の詳細は随時双方の協議により決定し、当該内容に基づき制作を実施するものとする。 |
| 納品日・検査期間 | 納品日:●年●月●日 検査期間:納品日から●営業日 |
| コンテンツの修正等 | 修正は動画編集作業についてのみ、原則として1回までとし、これを超える修正または撮影の再実施等は別途費用とする。 |
| 納品方法 | 検査完了後、上記各媒体でコンテンツを公開したことをもって納品完了とする。 |
| 公開期間 | 公開日:●年●月●日(予定) 公開期間:公開日から1年間を公開保証期間とする。 |
② 委託料(報酬)についての定め
PR業務委託契約においては、PR業務への対価として、広告主からインフルエンサーに対して一定の報酬が支払われることが一般的です。
報酬額については、もっともシンプルなのは「報酬は金●円とする」のように予め金額を明確に決める方法です。
ただし、PR業務委託契約においては、「PR動画公開時点におけるチャンネル登録者数×●円」のように、チャンネル登録者数、フォロワー数、平均再生回数などの指標を基に金額を決定するという方式が採用されることも多々あります。
この場合、指標となる数値をいつの時点のものとするか、数値を相互にどのように確認するかを明確に定めておくと、トラブルの予防に繋がります。
以下、この方法を採用する場合の条項例を紹介します。
第X条(報酬)
1. 広告主は、インフルエンサーに対し、本件業務の対価として、本配信の開始時点における本チャンネル等のチャンネル登録者数×●円(税別)を報酬として支払うものとする。
2. 広告主は、前項に定める報酬を、本配信の開始日が属する月の翌月末日までにインフルエンサーの指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。なお、振込手数料は広告主の負担とする。
3. インフルエンサーは、本配信実施後、直ちに当該時点でのチャンネル登録者数その他広告主が指定する事項(当該事項の根拠となる資料を含む。)を広告主に対して報告しなければならない。インフルエンサーが当該報告を怠ったことにより本配信時点でのチャンネル登録者数その他報酬の算定に必要となる事項が広告主において確認できない場合、広告主は、合理的根拠に基づいて報酬額を算定することができるものとする。
このほか、「PR動画を経由して発生した対象商品の売上額の●%」のように、成果報酬制が採用されるケースもあります。
この場合、PRを経由した売上額をどのように双方で共有・確認するか、成約したが入金に至らなかった場合はどのように取り扱われるかなど、決めておくべき事項が多々あります。
漏れがあると後々のトラブルの種となりますので、可能であれば弁護士に相談しながら条項を作成したほうが良いと思います。
③ コンテンツの権利帰属・二次的利用
多くの場合、PR動画などのコンテンツは、インフルエンサーの保有するアカウント・チャンネル等にて配信されることになるかと思います。
これに加えて、広告主としては、PR動画を広告主側のチャンネルでも配信したり、サムネイル画像や切抜・編集したコンテンツを利用するなど、広告主側でもPR動画等のコンテンツを自由に利用したいと考えるケースもあります。
これに対し、インフルエンサー側としては、広告主側でコンテンツを利用するのであれば別途料金が発生する形としたい、と考えているケースも多いと思われます。
また、広告主側での利用自体は容認したとしても、コンテンツを意図しない趣旨・内容に改変されたり、まったく違う商品の広告宣伝に利用されたりすると話が違ってくる、という場合も多いでしょう。
このような「二次的利用」については、そもそも可能であるのか、可能である場合はどのような範囲で認められるのかを明確にしておかないと、トラブルに発展しがちです。
以下は、コンテンツに関する権利(著作権、肖像権やパブリシティ等)はインフルエンサー側に帰属することを明確にしたうえで、別途配信や編集・改変等の二次的利用を行う場合には、別途協議の上で条件を決定するという趣旨の条項例です。
この記載例を参考に、コンテンツの権利帰属と二次的利用の範囲は明確に定めておきましょう。
第X条(本コンテンツの権利帰属)
1. 本コンテンツに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、肖像権、パブリシティその他の権利は、インフルエンサーに帰属するものとする。
2. 広告主による本コンテンツの配信、編集、改変等の二次的利用は本契約の範囲に含まれず、広告主が本コンテンツを二次的に利用しようとする場合、事前にインフルエンサーと協議の上で当該二次的利用の条件を決定するものとする。
④ 競合商品・サービスへのPR出演の可否(競業避止義務)
インフルエンサーが競合商品やサービスのPRを行うことを認めるか否かは、広告主側とインフルエンサー側で認識が違っていることが珍しくありません。
典型的なのは、広告主側は競合商品のPRがNGであることは「暗黙の了解」である、というような認識を持っている一方で、インフルエンサー側は、契約書上明記されていない以上、競合商品のPRは禁止されていない、と認識しているようなケースです。
近時、競合商品への広告出演を巡る裁判例も出てきています。
参考になると思われますので、少し内容を見てみましょう。
【事案の概要】
長年にわたりA社の「栄養ドリンク」の広告に起用されていた著名なサッカー選手が、B社の製造販売する「錠剤」タイプの健康食品の広告に出演したところ、これはA社商品への広告出演等に関する契約上の競業避止義務に違反するものではないかが争われた。【裁判所の判断】
–東京地裁令和4年12月22日判決(令和3年(ワ)868号損害賠償請求事件,D1-Law.com判例体系 ID:29075120)
A社の契約締結時に、競業避止義務の範囲を巡る交渉が行われており、その際、選手側から、競業避止の指定商品として「清涼飲料」の他に「食品」を追加するのであれば、契約金の追加が必要であるとの意向が示されたが、最終的に契約金は追加されることはなく、指定商品に「食品」が追加されることもなく、契約締結に至った。
裁判所は、これらの経緯も踏まえ、競業避止義務の対象に錠剤を含む「健康食品」は含まれておらず、B社の健康食品の広告に出演したことはA社に対する競業避止義務には違反しないと判断した。
上記の事例では、契約交渉時の経緯等も踏まえ、最終的には契約書の文言によって競業避止義務の範囲が確定されています。
したがって、「暗黙の了解」に過度に期待することは非常に危険と言えます。
「契約書に書かれていないのだから、競合のPRに出演しても問題ない」と捉えられてもおかしくはない、ということです。
広告主側としては、競合商品・サービスのPRを禁止したいのであれば、契約書上必ず明記する必要があると認識しておきましょう。
インフルエンサー側としても、仮に競合商品・サービスのPR禁止条項が定められていなかったとしても、競合他社のPRを行っても問題ないかは確認しておくべきと言えます。もしその結果、競合他社のPRは辞めてほしいとの意向が示されたとしても、上記事例の通り契約金額などの契約条件の交渉材料にすることも考えられます。
以下、競合商品・サービスのPRを禁止する場合の一般的な条項例を記載しておきます。
第X条(競業避止義務)
1. インフルエンサーは、本配信の公開保証期間中、広告主と同業種の第三者又は広告主と同種もしくは類似の商品を製造もしくは販売する第三者の広告宣伝に出演してはならず、またインフルエンサーの肖像、音声、氏名、名称等を使用させてはならない。
2. インフルエンサーは、前項に該当するか否かの判断が困難な依頼を第三者から受けた場合、遅滞なく広告主に通知し、双方の協議によりその可否を決定する。
場合によっては、PRが制限される商品・サービスの範囲をより厳密に定義したり、PR禁止の期間をいつまでとするか等の調整が必要になる場面もあるかと思います。
上記事例でも、競業禁止の範囲の定義が判断を分けた重要なポイントになっていますので、弁護士に相談しながら慎重に条項を検討することをお勧めします。
⑤ 不祥事・イメージ低下等の対策
インフルエンサーへのPR依頼は、インフルエンサーが有するイメージや好感度を前提に、商品・サービスの認知度やイメージの向上を狙いとして行われることが通常です。
そのため、インフルエンサーによる違法行為や不祥事、炎上など、イメージや好感度等が著しく低下するような事象が発生・発覚した場合には、広告主の商品・サービスのイメージにも大きな悪影響を及ぼす場合があります。
このような事態に備えて、前提として、景品表示法などの法律違反や商品・サービスのイメージを著しく毀損するような言動を行わない義務があることを明確にするとともに、万一発生した場合には、PR動画の取下げなどの措置を講じることができるようにしておくこと、報酬の返金や損害賠償を求められるようにしておくことが考えられます。
以下は、上記の趣旨を踏まえた条項例の一案です。
第X条(イメージ・信用の保持)
1. インフルエンサーは、本件業務の遂行にあたって、景品表示法その他の法令を遵守するとともに、ステルスマーケティングその他の消費者の誤解を惹起し、又は広告主の信用を著しく失墜させるおそれのある表示等を行ってはならない。
2. インフルエンサーは、広告主及びその関係者等の企業、商品、サービスのイメージや信用を毀損するような言動を行ってはならない。
3. 広告主は、インフルエンサーによる前2項の違反行為または違法行為、不祥事等の社会的評価またはイメージを著しく害する行為の発覚により、広告主の広告宣伝を著しく阻害するおそれがあると判断した場合、インフルエンサーに対して、速やかに本件業務の停止及び本配信の公開停止等の措置を講じるように請求することができる。
4. 広告主は、前項の措置により本配信の公開が停止となった期間、公開保証期間を基準として日割計算により報酬の支払義務を免れるものとする。第X条(損害賠償)
広告主及びインフルエンサーは、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、弁護士費用その他専門家費用及び逸失利益を含まない。)を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、損害賠償額は、相手方に故意または重大な過失がある場合を除き、本契約に定める報酬の●倍に相当する金額を上限とする。
「損害賠償」の項目について、少し補足をしておきます。
前提として、イメージ毀損や炎上に伴う損害は予測が立ちにくいという性質があります。
例えば、インフルエンサーの炎上を原因として、広告主の商品の不買運動に発展したというようなケースや、商品を購入した消費者からの返品・返金や在庫の廃棄が大量に発生したというようなケースでは、損害額が極めて多額なものとなってしまうケースもあり得ます。
そのため、特にインフルエンサー側としては、賠償責任が広くなりすぎないようにケアをしておきたいところです。そこで、条項例でも、損害賠償の金額には一定の上限額を設ける形としています。
これに対し、広告主側としては、どのような損害が想定されるかを可能な限り予測しつつ、どこまでの譲歩が可能かを慎重に検討していくことになります。また、条項例の通り、インフルエンサーがPR対象の商品・サービスへの誹謗中傷を行うなど、「故意または重大な過失」により損害を与えた場合には上限額は適用されない、といった文言を入れておくことは必要となるでしょう。
まとめ
以上、「PR業務委託契約書」のポイントと条項例を解説しました。
この記事で示した重要なポイントを押さえて、双方の利益やリスクをうまく調整し、双方が納得できる契約書を作成することが、広告主とインフルエンサーとの信頼関係・協力関係を構築するための第一歩となるはずです。
ぜひ、「暗黙の了解」に期待しすぎず、しっかりと契約書を作成することをお勧めします。そして本記事が少しでもその参考になれば、これに勝る喜びはありません。

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。