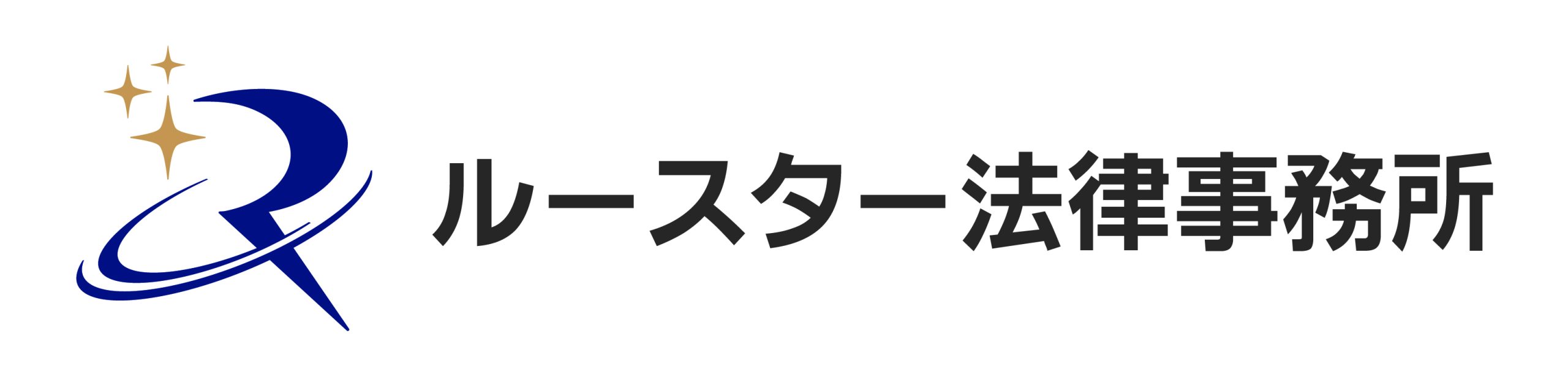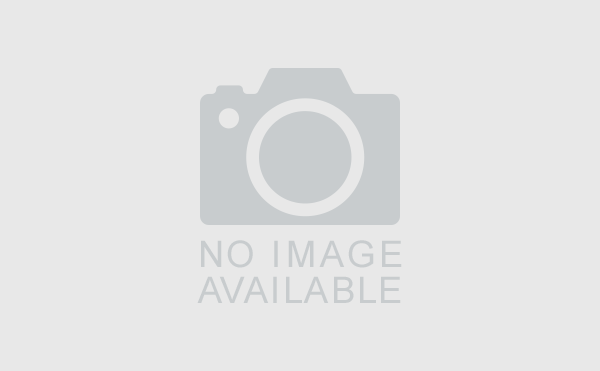紹介・仲介契約における「中抜き行為」と条件成就妨害
- 最高裁昭和45年10月22日判決(民集第24巻11号1599頁)
不動産仲介、人材・顧客紹介、代理店契約など取引の仲介や紹介を目的とする契約において、当事者が仲介業者を飛ばして直接契約を成立させ、仲介手数料や紹介手数料の支払いを免れることを画策するケースがあります。
これは「中抜き」や「直接契約」などと呼ばれ、仲介手数料や紹介手数料をマネタイズポイントとする業者にとっては必ず対策を考えておかなければならない重要な問題です。
しかし、仲介・紹介にかかわる契約書を締結していなかった場合や、契約書を締結していても直接取引を禁止する条項が定められていなかった場合はどうなるのでしょうか?中抜きされても諦めるしかないのでしょうか?
また、中抜き行為の抑止や責任追及のためには、どのような点に注意しておけばよいでしょうか?
今回は、仲介・紹介業者が中抜き行為に対抗する上で是非とも知っておきたい裁判例を紹介します。
事案の概要
①不動産仲介業者(X社)は、不動産の購入希望者(Y)から依頼を受け、仲介活動を実施していた。ただし、仲介契約書は締結されていない。
②X社は売却希望者(Z)を発見し、その後も仲介活動を続け、YZ間の売買契約締結直前まで至った。
③ところが、仲介依頼者であるYから、仲介活動をストップするよう要望があり、やむなくX社は仲介活動を中止した。
④後日、YとZとの間で、当該不動産につきX社を飛ばして直接売買契約が締結されていたことが判明した。
⑤そこでX社は、Yに対して、仲介報酬の支払いを求めて提訴した。
⑥これに対してYは、改めてZと直接交渉して購入が決まったのであって、X社の仲介活動によって購入が成立したわけではないから、仲介報酬は発生しない等と主張して争った。
判決の要旨
裁判所は、前提として、契約書が締結されていないとはいえ、XとYとのやり取り等から、【Yが目的不動産を購入することの仲介をX社に依頼し、購入が成立した場合には、報酬として取引価額の3%パーセントに相当する金額をYからX社に支払う】という内容の仲介契約が成立していたと認定しました。
しかし、それだけではまだ不十分です。
Yは「改めて直接交渉し、購入が決定したものである」と主張しています。
仲介報酬は「X社の仲介によりが売買が成立した」ことを条件として発生しますので、X社としてはこの点をクリアしなければなりません。
この「X社の仲介により売買が成立した」と言えるかという点につき、裁判所は以下のように判示し、YがX社に対して仲介報酬を支払う義務があることを認めました。
Y及びZは、Xの仲介によって間もなく契約の成立に至るべきことを熟知しながら、Xの仲介による契約の成立を避けるためXを排除して直接当事者間で契約を成立させたものであつて、Y及びZにはXの仲介による土地売買契約の成立を妨げる故意があったものというべきである。
(筆者により適宜要約)
…そして、Yは上記のとおり契約成立という停止条件の成就を妨げたものであるから、Xは停止条件が成就したものと看做して報酬を請求することができる。
解説
本判決は、民法130条の適用により「Xの仲介による売買の成立」が満たされたとみなすことによって、Xの報酬請求権を肯定したものです。
民法130条(現行民法では第130条第1項に相当)とは、次のような規定です。
民法130条
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
要するに、「条件の達成を故意に妨害された場合には、条件が達成されたものと扱ってよい」ということを言っています。
これを本件の事例に即してあてはめます。
上記の通り、XとYとの間には、【Xの仲介により不動産の購入が成立すること】を条件として、YからX社に対して仲介報酬を支払うという内容の契約が成立していたと認定されています。
その状況下でYがX社を排除してZと直接契約を締結したことは、「Xの仲介による購入成立」という条件が成就(達成)されることを故意に妨害したものであるから、妨害された相手方であるX社は、「Xの仲介による購入成立」という条件が達成されたものとみなして紹介報酬を請求できる、というロジックです。
つまり、仲介・紹介事業者を飛ばして中抜き・直接取引が行われてしまった場合であっても、「仲介や紹介の成立を妨害した」ということが証明できれば、当初の約定通りに紹介料や報酬を請求できる可能性がある、ということになります。
実務上のポイント
冒頭の「契約書を締結していなかった場合や、直接取引を禁止する条項が定められていなかった場合、中抜きされたら諦めるしかないのか?」という問いに対する答えは、上記の通り、「紹介・仲介の成立を妨害されたと立証できれば、報酬請求できる可能性はある」というものになります。
ただし、その立証は容易でないケースも多いと思われます。
本事例では、YとZとの間の直接契約がXによる仲介活動中止の直後に行われていたことや、購入金額も、Xの仲介により内定した額から少し上乗せされた金額であったことなどを指摘したうえで、Yには仲介による購入成立を妨害する(仲介報酬の支払いを免れる)意図があったと認定しています。
つまり、直接契約が行われたからと言って直ちに条件成就妨害になるとまでは言っていません。
実際、紹介から数ヶ月~1年経ってから直接取引が成立したようなケースだと、「たまたま別の機会で接触し取引に至っただけで、紹介料を免れようというつもりはなかった」といった反論を覆すことは容易ではないでしょう。
したがって、中抜きや直接取引を防止したり、紹介料をきちんと請求するためには、やはり事前に対策を講じておくことが重要です。
まず、仲介・紹介にかかわる契約書をきちんと締結しておく必要があることは言うまでもありません。
報酬について口約束で紹介活動をしていたら、いつの間にか直接取引されて紹介料を逃してしまった、というのはどの業界でもよく聞く話です。
加えて、契約書を締結する際、「直接取引を行った場合、紹介から一定期間内であれば報酬の対象になる」という条項を定めることも非常に有効です。
このような条項を「オーナーシップ条項」と呼ぶことがあります。具体的には、以下のような規定です。
紹介者が委託者に見込顧客を紹介した時から●ヶ月以内に委託者と当該見込顧客との間で本サービスの利用契約の締結に至った場合、紹介者の紹介に基づいて本サービス利用契約が成立したものとみなし、委託者は第●条に定める紹介料全額を紹介者に対して支払うものとする。
もっとも、「報酬の支払いを求めることができる」というだけでは、直接取引の抑止には不十分なケースもあります。
「直接取引が発覚しても、元々支払うべき報酬を支払えば足りる」と捉えられてしまう可能性があるためです。
そこで、直接取引など報酬の支払いを免れる行為があった場合、報酬に加えて違約金を請求できると定めておく方法があります。
例えば、次のような条項です。
委託者が、見込顧客との間で本サービス利用契約を締結したにもかかわらず虚偽の報告を行うなど、紹介者による紹介料その他の債務の徴収を妨げる行為を行った場合、委託者は紹介者に対して、第●条に基づき支払うべき紹介料に加えて、違約金として紹介料と同額の金額を支払う義務を負う。
このように、元々支払うべき報酬に加えてペナルティを設定しておき、直接取引等を行うメリットよりも発覚した際のデメリットの方が大きいと感じさせることにより、報酬を免れる行為を抑止する効果が期待できます。
まとめ
本記事では、仲介・紹介業務における「中抜き行為」とその対策について、具体的な裁判例をもとに解説しました。
このケースから学べる重要なポイントとして、たとえ契約書が存在しない場合でも、条件成就妨害が認められる場合には報酬を請求できる可能性があることが挙げられます。
ただし、それを証明するためのハードルは決して低くありません。
したがって、こうしたリスクを防ぐためにも、事前に契約書を適切に整備し、オーナーシップ条項や違約金条項を盛り込むことが重要です。
これにより、仲介・紹介業務の安全性を高め、報酬請求を確実にするだけでなく、不正行為の抑止効果も期待できます。

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。