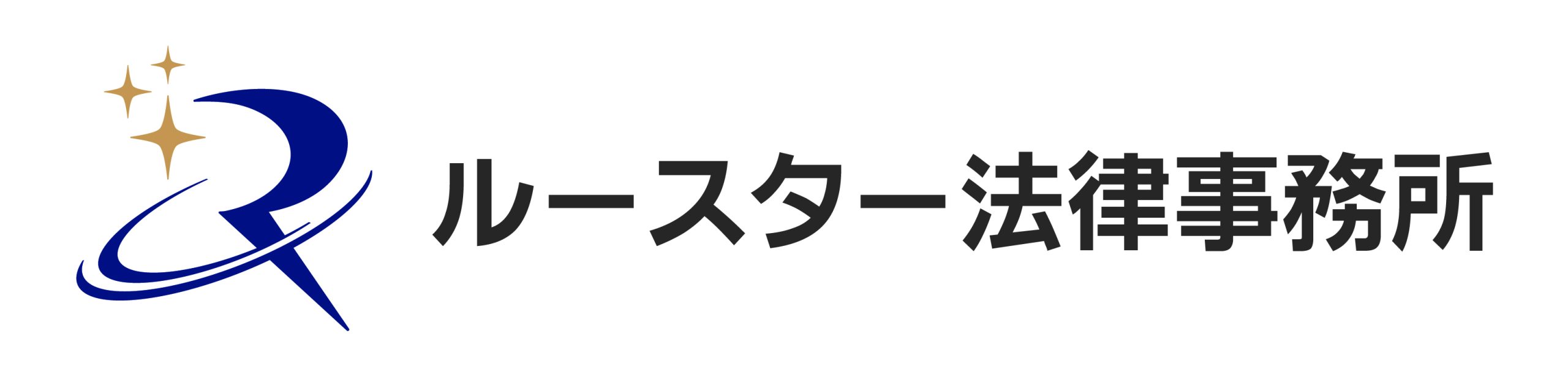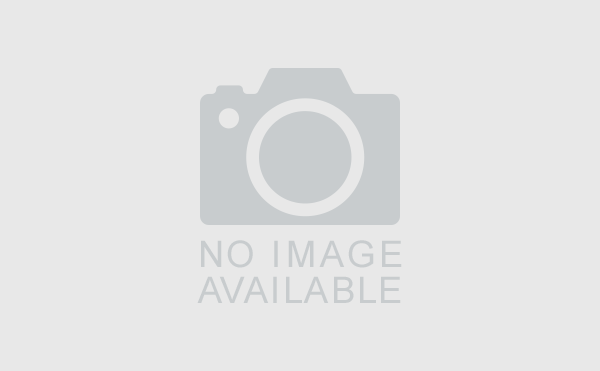「顧問契約書」「コンサルティング契約書」のポイントとひな型を解説【税理士、会計事務所、コンサル会社向け】
こんにちは。ルースター法律事務所 代表弁護士の山本です。
今回は、税理士や会計事務所などの士業事務所、経営、M&A、人材採用、広告・営業など各種コンサルティングを事業内容とする会社の皆さま向けに、「顧問契約書」「コンサルティング契約書」のポイントと条項例を解説していきます。
顧問・コンサルティングは、類型的に「どこまでが業務・報酬の範囲内か」「どこまで責任を負うのか」を巡ってトラブルが発生しやすい取引です。
本記事では、なぜこれらの取引においてトラブルが発生しやすいのかを明らかにしたうえで、どのようなポイントに注意すればトラブルを防止することができるかを解説していきます。理論や法解釈の問題よりも、実際の契約トラブルやリスクに根ざした、実務で本当に役に立つ解説・条項例の提案を試みるつもりです。
顧問・コンサルティング契約では、契約書の設計ひとつで業務の生産性や適正な報酬請求の可否が大きく左右されます。
また、自社を守りつつ、クライアントの利益にも配慮した公正な契約書を使用することは、専門家としての信用を高め、クライアントと信頼関係を構築していく上でも大いに役立つはずです。
契約書の整備をこれから進めたい方も、すでに契約書を運用されている方も、ぜひ参考にしてみてください。
- 1. 顧問契約・コンサルティング契約のポイント
- 1.1.1. 顧問契約・コンサルティング契約はなぜトラブルが発生しやすいのか
- 1.1.2. 顧問・コンサルティング契約書のポイント
- 1.1. 「業務の範囲」の定め方
- 1.1.1. ①業務時間の上限を定める
- 1.1.2. ②業務提供の方法を限定する
- 1.1.3. ③手続や段階で区別する
- 1.1.4. ④相談元・依頼元を集約する
- 1.1.5. ⑤基本契約+個別契約方式を採用する
- 1.1.6. 条項例
- 1.2. 免責・非保証条項の定め方
- 1.2.1. ①委託者(クライアント)側に落ち度、原因がある場合は免責とする
- 1.2.2. ②想定外の外部環境(法改正・市場変動等)による場合は免責とする
- 1.2.3. ③将来事象、不確定事象を保証しないことの明記
- 1.2.4. ④損害賠償の範囲(限度額)
- 1.2.5. 条項例
- 1.3. 契約期間、解除、中途解約のルール
- 1.3.1. 条項例
- 2. その他(権利帰属、再委託など)
- 3. まとめ
顧問契約・コンサルティング契約のポイント
顧問契約・コンサルティング契約はなぜトラブルが発生しやすいのか
顧問契約・コンサル契約においてトラブルが発生しやすい理由は、その特徴から理解することが可能です。
第一は、「無形の業務を目的とすること」です。
例えば、経営コンサルティングであれば「売上の増加・経費の削減に有効な施策の提案・支援」、税務・会計であれば「節税や株式評価の抑制のために有効なスキームの提案・支援」、広告であれば「広告効果を最大化するための運用方法の提案・支援」などが典型的な内容になります。
このように、スキーム・施策の「提案」やその実行に際しての「支援」と言った、「目に見えない」知見の提供そのものが契約の対象となることが一般的です。
したがって、物品やコンテンツ、システムと言った「目に見える物」の取引と異なり、何が契約の対象となっているかを当事者間で齟齬なく共有することが本来的に難しいという問題があります。
加えて第二に、「受動的・流動的に業務が発生すること」が非常に重要なポイントです。
顧問契約では、そもそも「クライアントからの相談や質問に専門的知見から回答すること」、つまり受動的に対応を行うことがメインの業務として想定されることが一般的と思われます。
提案・支援型のコンサルティングにしても、施策を実行していくにあたって生じた疑問への回答を求められたり、新たに生じた課題への解決方法の提案を求められたりと、受動的に業務が発生することは多いと思われます。
そして、いずれの類型でも、クライアントの経営状況、事業計画、業界動向、新規事業への参入、ステークホルダーの変化など様々な要因によって依頼、相談、解決すべき課題の内容・ボリュームがガラッと変わったり、求められる業務の内容・水準が変動したりと、業務の内容や範囲が流動的になることも珍しくありません。
上記の理由から、「何に対しての提案・支援を行う義務があるのか?」「どこまでの相談・依頼に対応する義務があるのか?」など、「業務の範囲内/範囲外」を巡る認識の相違がトラブルの原因になりがちです。
コンサルタント・士業事務所側の視点で言い換えると、「どこまでを業務の範囲内とするか」を上手くコントロールできないと、業務負担が増大し、取引自体が赤字となってしまいかねません。「業務負担が当初の想定・見積もりを超過した場合には、契約書に基づいて、報酬の見直しや追加報酬の請求を求めることができる状態」を確保しておくことが理想です。
顧問・コンサルティング契約書のポイント
上記の理由から、顧問・コンサルティング契約書においては、「対応業務の範囲」をいかにコントロールするか、という点が極めて重要なポイントとなります。
また、助言・指導の内容が高度に専門的であったり、新規性の高いものであればあるほど、助言通りの成果が得られなかった場合や、法令に抵触してしまった場合などに責任を問われるリスクも高まります。
したがって、「どこまで責任を負うか」(損害賠償、免責・非保証条項)をどのように設計するかも、非常に重要な課題と言えます。
その他にも、顧問・コンサルティングは一定期間の業務遂行を前提とすることがほとんどであるため、契約期間中の解約や返金などに関するルールを整理することも必要です。また、助言・指導の内容、報告書・提案書などの成果物の権利の帰属や目的外利用の禁止なども定めておく必要があるでしょう。
以下、上記で挙げた特に重要なポイントに絞って、契約条項を作成する上で注意すべきポイントと具体的な条項例を解説していきます。
「業務の範囲」の定め方
上記でも述べた通り、顧問契約・コンサルティング契約は「助言・指導、相談対応、提案」などの無形のサービスを提供する契約です。
加えて、クライアントから相談・依頼などを起点として「受動的・流動的」に業務が発生するという特徴を有しています。
そのため、契約の対象となる業務の範囲はどこからどこまでなのかが非常にあいまいになりがちです。
したがって、契約の対象となる「業務範囲」をいかにコントロールするかという点については、特に丁寧に設計する必要があると言えるでしょう。
しかし、「受動的・流動的」に業務が発生するという性質上、どのような業務がどの程度発生するかを完全に予測することは不可能です。
そこで、以下のようなアプローチにより業務範囲をコントロールすることが考えられます。
ポイントは、業務量や範囲は変動するものであるということを前提として、変動した際に追加料金や料金体系の見直しの糸口をいかに確保しておくかという点にあります。
どれか一つを選択するというわけではなく、実態に合わせて適切なアプローチを複数組み合わせて採用することがおススメです。
①業務時間の上限を定める
実際に業務に要する時間をカウントし、対応時間が一定の上限を超えたら追加料金が発生する、というアプローチです。
どのような顧問契約・コンサルティング契約においても採用可能な方式ですが、時間の集計等管理の問題が生じたり、具体的にどの程度時間を要したかはクライアントからは見えにいため、追加料金を請求すると伝えても理解を得られない場合も多く、想定通りに運用することは意外と難しいというのが実感です。
とはいえ、「目安」として対応時間を記載しておくだけでも、報酬の見直しや増額に向けた協議の足掛かりにはなりますので、規定しておく価値は十分にあります。
②業務提供の方法を限定する
例えば、「月1回開催する定例ミーティングにおいてアドバイスを実施する」「●月●日までに報告書を提出する」などのように、業務の提供方法を限定しておき、それ以外の業務や対応などは契約の範囲外(別途料金)とする、というアプローチです。
以前の記事で紹介した裁判例においても、契約書上に「コンサルティング業務は定例会議の開催により実施する」という文言があったことを理由に、コンサルティング会社にはそれ以外のアドバイスや業務を実施する義務は認められないと判断したものがあります。
(→参考記事:「コーチ・コンサルタントが「契約書」をキチンと固めておくべき理由を実際の裁判事例を基に解説します。」)
このように、業務の提供方法を明確にしておくことで、追加料金の請求にもつなげやすくなるとともに、いざという時の盾としても機能してくれることが期待できます。
③手続や段階で区別する
我々弁護士の顧問契約を例にとるなら、「相談」「契約書作成・チェック」など後方支援の段階であれば顧問料の範囲内で実施するが、「代理人交渉」「法的手続の遂行」などの手続を行う場合は別途料金とする、と言うように、支援の段階や手続の有無などによって区別するというアプローチです。
このほかにも、例えば以下のような設定を考えることが可能です。
- 税理士の場合:毎月の財務相談・アドバイスは顧問料の範囲内だが、記帳代行、税務申告手続や各種申請書類の作成は別途料金と規定
- 広告コンサルティングの場合:広告運用に関する助言・提案は委託料の範囲内だが、運用代行を受託する場合は別途料金と規定
- 営業コンサルティング:営業方法に関する助言・指導は委託料の範囲内だが、営業代行・顧客紹介を行う場合は別途料金と規定
④相談元・依頼元を集約する
1社の顧問・コンサルティングを実施する場合でも、部署が複数あり、それぞれの部署から独立して相談・依頼が寄せられる場合、業務負担としては2社分以上になってしまうというケースもあります。
そこで、依頼や相談の担当者を集約しておき、もし別部門・別担当者からの継続的な依頼が発生するようになった場合には報酬を見直す、というような規定を入れておくと、業務範囲をコントロールする上で有効な場合があります。
⑤基本契約+個別契約方式を採用する
上記の通り、顧問・コンサルティング業務は流動的になりがちという特徴があります。
1ヶ月あたり10時間程度を想定していたのに、実際には20時間以上要しているとか、定期ミーティングでの助言をメインと想定していたのに、実際には相談対応の方が多くなっているとか、当初の想定と実際の業務負担がズレることは往々にしてあり得ます。
したがって、一定期間ごとに報酬体系を見直す糸口を確保しておくことが重要です。
この点については、基本契約書の中で大枠の業務内容を定めつつ、実際の対応範囲や時間数、提出物の内容などは、別途「個別契約書」や「発注書」によって明示する形式がおすすめです。
例えば、「3~6か月単位で発注書を交わす」といった運用を行えば、期間中の業務実績などを踏まえ、「次期の発注は報酬を見直してほしい」などのやりとりもスムーズになることが期待できます。
条項例
具体的な条項や発注書ひな型を作成するにあたっては、自社の顧問・コンサルティングの内容や想定される提供方法を踏まえ、上記のアプローチを組み合わせて業務の範囲をコントロールするための仕組みを検討していくことになります。
以下、一つの例として、上記を契約条項に落とし込んだ条項例・発注書記載例を提示しておきます。
これを参考にして、自社の事業に即した最適な契約条項を検討していただければ幸いです。
第●条(業務委託)
1. 委託者は、次の●●顧問業務(以下「顧問業務」という。)の遂行を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(1) ●●にかかる助言、指導その他の支援
(2) ●●の作成
(3) 各種申告書等の作成代行
(4) 専門的知見の共有
(5) 前各号の業務遂行のために必要な資料等の作成
2. 具体的な顧問業務の内容、範囲、遂行方法、期間等については、別途個別契約により定めるものとする。
3. 前項の個別契約は、別途委託者が所定の発注書(電磁的方法を含む。以下同じ。)により発注し、受託者がこれを承諾することによって成立する。第●条(委託料)
1. 委託者は、受託者に対し、個別契約で定める委託料を、個別契約で定める支払期限までに、受託者の別途指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、委託料の振込にかかる手数料は委託者の負担とする。
2. 受託者は、委託業務の変更、経済情勢、その他の合理的な事由が生じた場合、委託者に対し、委託料の変更のための協議を申し入れることができるものとする。
◆発注書(個別契約書)記載例
| 委託期間 | ●年●月●日~●年●月●日(●ヶ月間) | 当事者双方から特段の意思表示がない場合、委託期間満了後も本発注書記載の内容と同一の条件・期間により更新され、以降も同様とする。 |
| 委託業務内容 | ●●に関する相談・質問対応 | ●●に関する委託者の相談・質問に対し、受託者の専門的知見を基に回答を行う業務 回数・方法・相談時間についての上限は特に定めないが、相談者は担当者1名を想定するものとし、相談者が増加する場合には報酬形態の見直しを実施するものとする。 |
| ▲▲に関する施策提案・支援 | 原則として1ヶ月につき1回、1回あたり●時間を目安とする定例会議(オンラインを含む)の開催により実施する。 受託者は、定例会議の実施後遅滞なく議事録を作成の上委託者に提出する方法により、業務遂行状況を報告する。 議事録の提出後●日以内に委託者から特に異議が述べられない場合、当該業務は本契約に従って履行されたものとみなす。 なお、施策の実施に伴い各種申請業務、書類作成業務、面談同行等の別途業務が発生する場合は、別途協議の上で定める報酬が発生するものとする。 | |
| ■■に関するチェック | ■■に関する書面、文章の内容や手続等について、受託者の専門的知見を基に意見を述べ、必要に応じて追記、修正等を行う。 対応時間(調査及び追記・修正等に要する時間も含む)は1ヶ月あたり●時間を上限とし、これを超過する場合には超過1時間あたり●●円を基準として追加報酬が発生するものとする。 なお、実際の対応時間が上限に達しなかった場合でも、翌月以降への繰越等は行わない。 | |
| 委託料 | 月額●●万円(税抜) | 当月末締め翌月末日支払とする。 |
- 相談・質問対応については相談元を集約する方法、施策提案(コンサルティング)については会議におけるアドバイス提供のみを契約業務とし、各種代行や書類作成等は別途報酬とする方法、文書等のチェックについては対応時間の上限を設ける方法により業務範囲のコントロールを試みています。あくまでも一例ですので、自社の事業内容等に沿って適切な設計に変更してください。
- 委託料は月額定額制方式としています。報告書等成果物の納品に応じて委託料を請求する場合は、成果物の確認・検収に関するルールを定めたうえで、検収完了の翌月末日までに支払、などの条件にすることが考えられます。
免責・非保証条項の定め方
顧問契約、コンサル契約においては、「助言・指導の通りに実行したのに、思っていたような成果が出なかった」と言ったような、成果を巡るトラブルが発生することがあります。
また、場合によっては、助言・指導の結果、クライアントに損害を与えてしまうというケースもあり得ます。例えば、「誤った内容の提案や、法律に抵触する提案をしてしまった」ケースなどが典型的です。
これらのトラブルにどのような方針で臨むかという視点は、顧問契約・コンサルティング契約の条項を検討する上で非常に重要な視点です。
一つのあり得る考え方としては、「何があっても一切の責任を負わない」といった広く強力な免責条項を設定するという方針があります。
しかし、あまりに一方的な免責条項ばかり並べると、無責任な印象を与え、クライアントとの信頼関係を損なうリスクがあります。
そもそも、一切責任を取らない専門家に誰が依頼するのか?という話にもなりかねません。
とはいえ、どんな場合にでも責任を負わなければならないという事態も避けなければなりません。
結局は、バランスの問題と言うことになると思います。
では、具体的にどのような条項にするとバランスが良いのか?という点については、取扱い分野、業務の性質、価格とのバランスを加味して、それぞれの事業者が考えて決定していくしかありません。
とはいえ、丸投げしたのでは記事を読んでいただいた意味がありませんので、検討の材料として、「このような視点で考えてみてはどうでしょうか?」「一般的にはこのような規定を設けることが多いですよ」と言った例を、少し整理してみたいと思います。
①委託者(クライアント)側に落ち度、原因がある場合は免責とする
顧問・コンサルティングは「提案・アドバイス」を本質的な内容とする契約です。
したがって、提案やアドバイスの前提となるクライアント側からの情報提供が不十分であったり、クライアント側が提案した内容とは異なる施策を実行したりする等、クライアント側の都合によりコンサルティングがうまくいかなかったというケースも想定されます。
このように、クライアント側の落ち度による成果不達成や損害の発生については責任を負わないと規定しておくのは有効な対策と言えます。
また、比較的クライアント側からの理解も得られやすいでしょう。
②想定外の外部環境(法改正・市場変動等)による場合は免責とする
アドバイスや助言が法律・慣行に関係する場合があります。各種士業はもちろん、広告コンサルであれば景品表示法、薬機法、公正競争規約等、採用コンサルティングであれば職業安定法など、法規制を意識してアドバイス等を行わなければならないケースがあります。
専門業者として、関連法令を把握し、それに従ったアドバイス等を行う義務があることは当然です。
しかし、法令や運用が変更されたり、新しい規制が定められることにより、それまで通用していた運用がある日突然違法なものになってしまう、といったケースもあり得ないわけではありません。
法令以外にも、パンデミック等の異常事態の発生、為替の急変や物価高騰といった市場要因、主要プラットフォームのポリシー改定など、受託者の合理的なコントロールを超える外部環境の変化により、当初の前提に基づく助言の効果が減殺される、又は実施不能となる場合も想定されます。
このように、想定外の外部環境の変化による成果不達成や損害の発生については免責とするといった条項を設定しておくことは、非常に有効なアプローチと言えます。
③将来事象、不確定事象を保証しないことの明記
基本的なスタンスとして、「成果や業績を保証するものではない」旨を契約書に明記しておくことは有効です。
特に営業現場では、案件を獲得するために売上や成果を約束するかのような表現を用いてしまうことが少なくありません。その結果、クライアントが成果保証が契約内容に含まれると誤解し、後のトラブルに発展するケースも散見されます。
もちろん、営業担当者がそのような過度な約束を行わないように社内で管理することが第一ですが、コンサルティング・顧問は成果や業績を保証するものではないというスタンスを明確にしておくことは、安全策として重要です。
④損害賠償の範囲(限度額)
少し視点は異なりますが、相手方に対して負う損害賠償責任に上限を設けるなどの方法によりリスク管理を行うことも考えられます。
ただし、一方的な免責・上限設定はクライアントからの不信を招く原因にもなりますので、設定する場合でも「故意または重大な過失の場合は除く」など、可能な限り公平な内容にしておきたいところです。
条項例
以下、上記を踏まえた免責条項の一例を示します。
自社の事業内容や、何に対してどこまで責任を負えるかなどを慎重に検討の上、適切な免責条項を設定するようにしましょう。
第X条(非保証)
1. 委託者は、次の内容をあらかじめ承諾するものとする。
(1) 関係資料等の提供が遅延した場合、関係資料等に不足、誤り等がある場合、受託者による顧問業務の遂行が遅延、不能となる可能性があること。
(2) 顧問業務が、本契約締結時の法令、実務、慣行に基づくものであり、将来的にその法令等が改廃・変更された場合、その結論に影響する可能性があること、及び当該改廃・変更に際し、受託者が既に提供した助言や提出物を随時更新する義務を負うものではないこと。
(3) 顧問業務に際し、受託者が委託者の事業計画、資金計画等の将来事象を提供する場合であっても、これらの達成可能性や将来予測については、受託者は責任を負わないこと。
(4) 委託者は自らの責任において受託者の助言・指導を採否するものであり、受託者は委託者に対して、委託者事業の業績等について何らかの保証等を行うものではないこと。第X条(損害賠償)
1. 委託者及び受託者は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して相当因果関係の範囲内で当該損害の賠償を請求することができるものとする。
2. 前項により相手方が負担すべき損害賠償の額は、委託料の総額(月額の場合は月額委託料の●●か月分)を上限とする。ただし、相手方に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。
契約期間、解除、中途解約のルール
顧問契約・コンサルティング契約は、多くの場合「一定期間契約関係が継続すること」を前提に設計されると考えられます。
契約関係が継続するからこそできるアドバイスもあるでしょうし、コンサルティングの内容等によっては、一定程度の期間をもって取り組まないと効果が見込めないと言ったケースもあるでしょう。
したがって、基本的なルールとして、契約がどの程度継続するかを明確にしておくことが必要となります。
他方で、様々な事情により、中途で契約が終了するケース、あるいは中途で契約関係を打ち切らなければならないケースも想定されるところです。
こうした事態に備えて、中途解約・解除はどのようなケースで可能か、その場合報酬などの取り扱いはどうなるか、と言った点を明確にしておくことが重要です。
以下、契約期間、中途解約、解除を巡る問題について、受託者側の視点に立ちつつ、クライアント側の利益にも配慮した条項例を紹介します。
条項例
第X条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了日の 1ヶ月前までに契約当事者のいずれかから別段の申出がないときは、自動的に同条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
2. 委託者及び受託者は、1ヶ月前までに相手方に対して書面をもって通知することにより、本契約を中途解約することができる。ただし、個別契約については、当該個別契約において定められた委託期間中、委託者及び受託者は当該個別契約を中途解約することはできないものとする。
3. 本契約の終了時に有効な個別契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該個別契約の遂行についてのみなお本契約が適用されるものとする。
- 中途解約は可能だが、すでに受発注済みの個別契約については中途解約不可とする場合の条項例です。少なくとも上記の「発注書」において定めた業務は発注をキャンセルされないようにすることを狙いとしています。
- 個別契約も含めて中途解約を許容する場合には、中途解約時における報酬等の清算について定めておくことが必要となります。月額報酬など定額制であれば、「中途解約により1か月に満たない期間が生じた場合、当該期間中の委託料は1か月を30日として日割計算した額とする」など、日割計算により清算する旨の規定を入れておくことが合理的なケースが多いと思われます。他方、業務完了や成果物納品に対する報酬(後払い)を採用した場合は、「中途解約がなされた場合、解約時点までの業務の遂行に対する対価について協議して算定し、その算定した価額を支払うものとする」など、報酬の一部を請求できるような規定を入れておく必要があります。
第X条(業務遂行の中止)
1. 委託者が委託料の支払いその他の本契約に基づく義務の履行を怠った場合、受託者は遂行中の顧問業務を直ちに中止することができ、当該義務が履行されたことが確認されるまで、顧問業務の遂行をしないことができる。
2. 前項の中止によって、委託者に損害その他の不利益が生じた場合であっても、受託者は一切の責任を負わないものとする。第X条(解除)
1. 委託者及び受託者は、相手方が本契約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後相当期間内に当該違反状態が是正されないときは、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本契約を解除することができる。
2. 前項に関わらず、委託者及び受託者は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(2)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4)租税公課の滞納処分を受けた場合
(5)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7)本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(8)刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
(9)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
(10)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
3. 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本契約に関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を一括して弁済しなければならない。
4. 本条第1項及び第2項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
- 受託者側の立場からすると、契約の解除を検討する場面として典型的なのは、顧問料やコンサルティング料などの支払いが滞った場合です。
上記条項例では、①契約自体は解除せず、委託料が支払われるまでの間業務を中止できるという規定と、②契約自体を解除するという2つの対応策を選択できるようにしています。いったん「顧問料が支払われるまで業務を停止します」と伝えて様子を見つつ、それでも支払いがなければ契約解除を実行するなど、柔軟な対応が可能となります。 - このほか、倒産や支払停止などの信用不安や、クライアントによる違法行為の発覚時なども契約解除を検討すべき場面です。業種によっては、クライアントの違法行為に自身が関与しているのではないかとの疑いを持たれるような可能性も懸念されます。このような場合には、即時に契約を解除できるという建付けを採用しています。
その他(権利帰属、再委託など)
その他にも、成果物などに関する権利の帰属をどうするかと言った問題や、業務を第三者に再委託する場合の秘密保持の問題などがあります。
これらの内容は以前に投稿した「業務委託契約書」一般についての解説と重複する点が多いため、さらに深堀したいという方は以下の記事も参考になさってみてください。
まとめ
顧問契約書やコンサルティング契約書は、「目に見えない」業務を対象とするものであるにもかかわらず、業務範囲があいまいなままで締結されるケースが少なくありません。
こうした状況は、「受動的・流動的」な業務の発生により業務負担と報酬とのバランスが失われる原因となったりするだけでなく、のちのトラブルの温床にもなり得ます。
本記事で解説した通り、以下のような論点は、認識のズレが生じやすい典型例です。
- どこまでが契約に含まれる業務か(業務範囲・スコープ)
- 時間や対応量が想定を超えていないか(工数管理・追加報酬)
- 成果が出なかった場合の責任の所在(免責・非保証)
- 契約終了時の取扱い(中途解約・返金・清算方法)
こうしたトラブルを未然に防ぐには、基本契約書で全体の枠組みを定めつつ、個別契約(または発注書)で具体的条件を明記する二層構造が有効です。これにより、業務範囲・責任分担・報酬計算・解約時の精算といった主要論点を事前に可視化することができます。
さらに、成果を保証しないこと、最終的な意思決定はクライアントにあることなど、顧問・コンサル特有の性質を踏まえた条項設計も欠かせません。
自社のサービス特性や業務実態に即した契約設計を心がけることが、円滑な顧客関係の維持・発展につながるでしょう。
自社のサービス特性に合わせて、実態に即した契約設計をぜひ意識してみてください。

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。