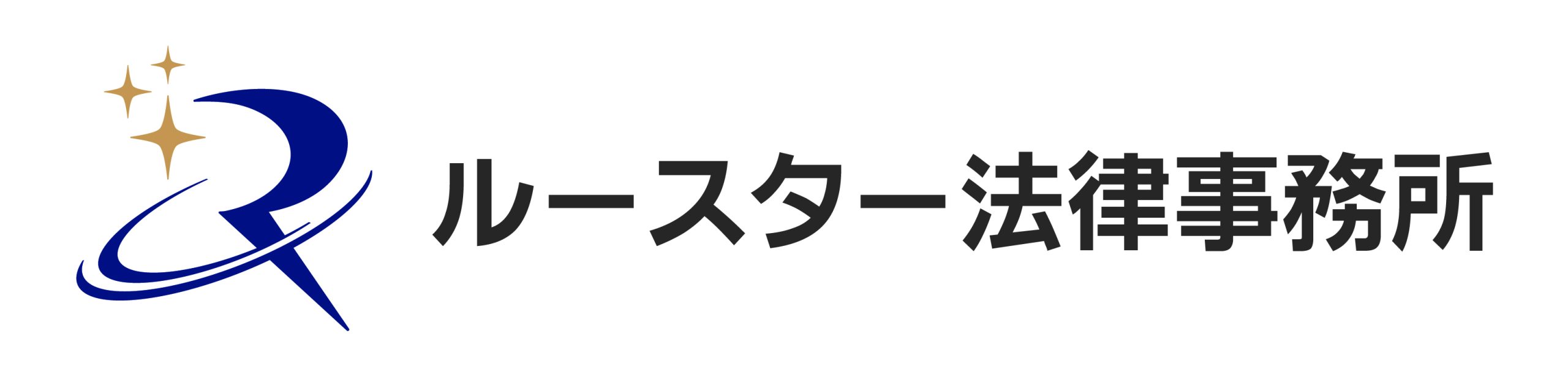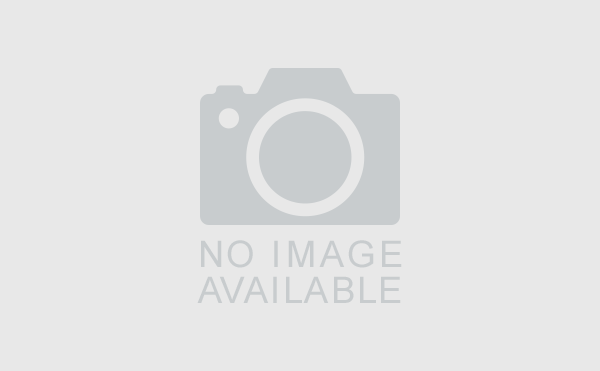「業務提携契約書」のポイントとひな型を解説 【販売提携/クーポン発行型】
こんにちは。ルースター法律事務所 代表弁護士の山本です。
自社サービスの販売促進や顧客層の拡大を図るうえで、他社と提携し、商品やサービスを相互に紹介・連携する「業務提携」は、とても有効な手段の一つです。
特に、自社の商品・サービスを販売する際に、他業種のサービスとセットで販売したり、クーポンや優待特典を共同で発行するような提携は、今までに獲得できていなかった層に直接自社商品・サービスを認知・体験してもらえる可能性があり、ユーザー層の拡大を図る上で非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。
このような販売提携/クーポン発行型の業務提携は、中小企業・ベンチャー企業やD2C企業、アプリ事業者の間でも、ますます増加傾向にあります。
しかし、こうした提携は、販売者・クーポン発行者と対象サービスの提供者が別々の事業者となるため、提携の範囲やユーザー対応などの役割分担が曖昧なまま進むと、トラブルや責任の押し付け合いに発展するリスクがあります。
今回は、このような販売提携/クーポン発行型の業務提携を行う上で必要になる契約書のポイントを、条項例を踏まえながらわかりやすく解説します。
業務提携契約とは?
「業務提携契約」は、複数の企業が特定の目的のために協力関係を構築するために締結される契約を指します。
一般的には、「資本提携」と区別する文脈で用いられることが多いようです。
つまり、株式の保有や出資、子会社化等を伴わず、あくまでもお互いの企業の独立性は保ったままで複数の企業が協力し合うことを「業務提携」と呼称することが一般的だと考えられます。
もっとも、厳密に定義された法律用語というわけではありませんので、複数の企業が協力関係を構築することを広く「業務提携」という、と言った程度のイメージで特に問題ありません。
また、「業務提携」という言葉は多義的で、その内容は提携の目的によって大きく異なります。例えば、
- 技術提携・共同開発
└ それぞれ異なる技術領域に強みを持つ企業が連携し、新技術を開発する形態 - 生産提携・OEM
└ 商品を企画した企業が、自社に生産設備を持たないこと等を理由に、他社に製造を委託する形態
このように、様々な協力形態を総称して「業務提携」と呼称されます。
したがって、一口に「業務提携」と言っても、その内容や目的によって、法的なリスクや契約上の注意点も変わってくる点には留意が必要です。
この記事では冒頭に触れた通り、特に「セット販売」や「クーポン発行」など、販売促進型の業務提携(販売提携)にフォーカスして解説していきます。
具体的には、ある企業(A社)が自社サービスを販売する際に、他社(B社)のサービスをセット販売として組み合わせ、無料クーポンを発行するキャンペーンを実施するという提携形態をモデルとして、契約書に記載すべきポイントや条項例を解説していきます。
他社サービスとのセット販売やクーポン提供を通じて販路拡大を目指している企業にとって、本記事の内容は非常に参考になるはずです。
実務上見落とされがちな契約上のリスクや、事前に取り決めておくべきポイントも整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 販売促進型の業務提携として、この他に、相手方の見込顧客を発見した場合に相手方に紹介・送客する「顧客紹介契約」や、相手方のサービスの販売権を授与してもらう「代理店契約」などがあります。これらについては↓の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
販売提携型業務提携契約の3つのポイント
ある企業(A社)が自社サービスを販売する際に、他社(B社)のサービスの無料クーポンを発行するキャンペーンを実行するためのA社・B社の役割分担を整理すると、おおむね次のようなフローが想定されます。
- A社は、セット商品を顧客に販売する際、対象となるB社サービスの無料クーポンを顧客に交付する。
- B社は、クーポンを持参・提示した顧客に対し、対象サービスを無料で提供する。
- A社は、B社に対して、予め決めておいた負担金(仕切価格)をクーポン利用件数に応じて支払う。
このような役割分担でクーポン発行事業を実施する場合、次のようなトラブルが発生することが懸念されます。
- クーポン発行・利用に関するトラブル
└発行上限を決めていなかったため、対応し切れない大量のクーポンを発行されてパンクしてしまう
└有効期間を明確にしていなかったため、長期間にわたって無料提供を余儀なくされる - 顧客対応やキャンセルに関するトラブル
└「追加料金を請求された」「対応が悪かった」などのクレーム
└顧客の無断キャンセルが発生。B社としては、予約枠を空けた分仕切価格をA社に負担してもらいたいと考えているが、A社はサービス提供が行われていないから支払い義務はないと主張している。 - 利用件数照合・仕切価格精算に関するトラブル
└A社がクーポンを発行した件数と、B社におけるクーポン利用件数が一致せず、仕切価格の精算ができない。
└B社がクーポン利用件数を水増しして仕切価格を請求している可能性があるが、明確な根拠がない
以上を踏まえると、クーポン発行・サービス提供をスムーズに行うためには、クーポンの発行上限数、利用条件や利用期間など、「クーポン発行・利用に関するルール」を明確にしておくことが大前提だということがお分かりいただけるかと思います。
また、販売者(クーポン発行者)とサービス提供者が異なるため、顧客対応やクレームなどへの対応、役割分担なども明確にしておかないと、現場での混乱や顧客からの信頼低下にもつながりかねません。
そして、クーポン利用に対する仕切価格の精算の場面も、件数相違や水増しなどのトラブルが起きがちなので、どのようなルールで処理するかを明確に定めておく必要があります。
以下、①「クーポンの発行・利用ルール」、②「顧客対応などの役割分担」、③「クーポン負担金・仕切価格の精算に関する事項」の3点を中心に、クーポン発行による販売促進型の業務提携契約におけるポイントと条項例を解説します。
なお、本記事では、便宜上上記で言うA社(セット商品の販売・クーポン発行を行う側)を「販売元」、B社(クーポン対象サービスを提供する側)を「提供元」と呼称することとします。
クーポンの発行・利用ルールの整備
上記の通り、クーポン発行による提携をスムーズに進めるためには、クーポンの発行数・発行条件、対象となるサービス、発行方法、利用条件、利用方法、利用期間などの「クーポン発行・利用ルール」を明確にしておくことが出発点となります。
これらが曖昧なまま進むと、対象外ユーザーへの提供、想定外の費用発生、提携終了後のクーポン利用など、様々なトラブルの原因となります。
クーポン発行の具体的な方法としては、紙媒体でクーポン券を交付する方法と、公式LINEなどプラットフォームの機能を用いてクーポンコードを発行する方法などがあります。どのような方法で発行するのかも、予め明確にしておくことが必要です。
また、決定した利用条件や有効期限については、それがクーポン利用者にも十分に周知されていなければ、現場での混乱やトラブルに繋がるおそれがあります。そこで、販売元がクーポン発行時に利用条件や有効期限等をきちんと案内し、説明する責任を負う形にすることも重要です。
以下、これらの「クーポン発行・利用ルール」を明確にするための条項例を紹介します。
なお、本条項例では、クーポンの詳細なルールや注意事項、仕切価格等について、別紙により明示する形を採用しています。別紙記載例については、後ほどまとめてご紹介します。
第X条(業務提携)
販売元及び提供元は、本契約に定めるところにより、販売元のサービスに関連して提供元が提供するサービスのクーポンを発行する事業を共同して実施することにより、当事者双方の利益拡大に資することを目的として、本業務提携を実施する。第X条(クーポンの発行・利用条件)
1. 販売元は、別紙「クーポン条件書」または別途双方合意の上で定めた条件および方法に従い、対象顧客に対して、本件サービスの利用に係るクーポンを発行することができる。
2. 販売元は、本件クーポンを対象顧客に発行する際、別紙「クーポン条件書」または別途双方が合意した内容によるクーポン利用条件(利用可能店舗・サービス、クーポン利用方法、有効期限等)を対象顧客に対して明示し、説明しなければならない。
3. 有効期限を経過したクーポンについては無効とし、販売元は、当該期間を過ぎたクーポンの利用について提供元に対して仕切価格の精算義務を負わないものとする。ただし、販売元による説明不備等、販売元の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
双方の役割分担の明確化
クーポン発行による提携スキームでは、クーポン発行と対象サービス提供時の現場対応が双方にまたがることとなるため、顧客への案内・説明内容とサービス提供時の対応とが食い違うなど、顧客対応に関するトラブルが往々にして起こり得ます。また、クーポン利用件数は後日の仕切価格の精算にもかかわるため、確実に回収・管理を実施する必要があります。
したがって、クーポン利用・サービス提供に伴う双方の役割分担・責任の範囲を明確にしておくことが、スムーズに提携を進める上で重要です。
以下、いくつかの重要な要素に分けて解説します。
- 料金・サービス内容
追加料金を請求されたとか、聞いていたのとは違うサービスを提供された等のクレームはその後のトラブルに発展しやすいので、これらが発生しないように対策を講じておくことが重要です。具体的には、「あらかじめ決めたサービスの内容・料金を変更なく提供しなければならない、対象顧客に対して追加費用を請求しない、通常の顧客に提供するサービスと同等の品質および対応水準により提供しなければならない」ことなどを義務付けることが考えられます。 - クレーム対応
実際にクレームが発生した場合の対応方針もあらかじめ定めておくことが重要です。クレームが発生した場合には双方に速やかに情報共有を行い、対応方針を決定することが鉄則となりますので、速やかな情報共有義務を定めておくことは必須です。加えて、クレーム解決に費用を要した場合の負担基準を定めておくとより効果的です。 - 予約キャンセルの取扱い
予約等を伴うサービスの場合、顧客のキャンセル時はどのように処理するのかという点も重要です。提供元としては、顧客のために予約枠を空けた分、仕切価格を負担してもらいたいと考えることが通常でしょう。他方、販売元としては、実際にサービスが提供されていない(クーポンが利用されていない)以上、仕切価格の支払いの必要もないと考えるのが通常と思われます。
こうした対立を未然に防ぐためにも、あらかじめ双方の落としどころを取り決めておくことが重要です。具体的には、「●日前までのキャンセルは対象外、●日前以降~当日のキャンセルは支払い発生」のように、キャンセルが行われたタイミングに応じて仕切価格の負担の有無を変える、などの方針が考えられます。 - クーポンの使用済み処理・回収、保管
後日のクーポン利用分の負担金・仕切価格の精算に備えて、クーポン利用件数を確実に残しておくことも重要となってきます。
紙媒体のクーポン券であれば、利用されたクーポン券を確実に回収し、保管すること、プラットフォーム等の機能を利用したクーポンコードであれば、「使用済み」の処理を確実に行うことなどをように義務付けておくことが重要になります。
以上のポイントを踏まえ、双方の役割分担に関する条項例を紹介します。
あくまでも一例ですので、実際の運用方針等に照らして、適宜アレンジしてご使用ください。
第X条(サービス提供および役割分担)
1. 提供元は、別紙「クーポン条件書」または別途双方の合意により定められた対象サービスの内容・料金その他詳細について、当該内容から変更なく提供しなければならず、対象顧客に対して追加費用を請求しないものとする。
2. 提供元は、クーポンを利用する対象顧客に対して、通常の顧客に提供するサービスと同等の品質および対応水準により対象サービスを提供するものとする。
3. 乙は、対象顧客が提示するクーポンの有効性を確認し、別紙「クーポン条件書」または別途双方合意の上で定める方法により使用済み処理を行うものとする。第X条(キャンセルの扱い)
対象顧客が予約をキャンセルした場合等の取扱いについては、別途クーポン条件書に定めるものとする。第X条(クレーム対応及び紛争処理)
1. 販売元及び提供元は、本提携に関連して第三者の権利を侵害し若しくは侵害するおそれがあることを知った場合又は本提携に関連して第三者からクレームを受け若しくはそれらの者との間で紛争を生じた場合は、直ちに相手方に通知するとともに、双方協力して処理解決を図るものとする。
2. 前項の紛争解決に費用を要した場合、費用の負担は次の通りとする。
(1) 紛争の原因が、専ら一方当事者に起因し、他方当事者に過失が認められない場合は当該一方当事者の負担とする。
(2) 紛争が当事者双方の過失に基づくときは、その程度により双方協議の上負担割合を定める。
(3) 上記各号のいずれにも該当しない場合、双方協議の上その負担割合を定める。
利用件数の確認と仕切価格精算のルール化
発行されたクーポンが利用された場合、顧客への代金請求は行わないか、割引金額を適用することになりますので、提供元としてはその差額分が得られないことになります。
この差額分につき、キャンペーン価格として提供元が負担することももちろんあり得ますが、クーポン利用件数に応じて、販売元が予め決めておいた負担金(仕切価格)を提供元に支払うというスキームが採用されることも多いと思われます。
このような場合、負担金(仕切価格)の精算についてのルールを明確にしておく必要があります。
単価を決定しておくことはもちろんですが、それと同じくらい、「クーポン利用件数をどのように照合するか」を決定しておくことが非常に重要です。
上記でも述べた通り、「クーポン発行」と「サービス提供」の窓口が双方にまたがるため、クーポンの発行ミス、利用時の確認ミス、管理ミスなどによって、どこかで双方のクーポン利用件数に関する齟齬が発生してしまうリスクは避けられません。
そのため、件数照合のルールが曖昧だと、「利用件数に疑義があるため精算に応じられない」などのトラブルに発展する可能性が高まってしまうことは容易に想像できます。
具体的には、まずはクーポンの発行・利用について定期的に情報共有を行う義務があることを明確にしておくことが必要となるでしょう。
加えて、利用件数に齟齬がある場合、何をもって確定件数と扱うかについても定めておくことが重要です。例えば、公式LINEなどプラットフォーム機能を用いたクーポン発行であれば、「使用済み処理の件数」などプラットフォーム上の数値をもって確定件数と扱う、紙媒体であれば、提供元が現実に回収・保管している使用済みクーポン券の枚数をもって確定件数とする、といった具合です。
また、精算の対象とならない例(未使用、不正、水増し、対象外サービスへの流用等)を具体的に明示しておくこともトラブルの未然防止に役立ちます。
以下、これらの趣旨を踏まえた条項の一例をご紹介します。
第X条(クーポン利用件数の照合)
1. 販売元及び提供元は、別紙クーポン条件書または双方合意の上で定める方法によりクーポン利用状況・利用者情報を相互に共有するものとし、毎月末日を締日として、当該月におけるクーポン利用件数の照合を行う。
2. クーポン利用件数等に関する相違があり、当事者間の協議によっても解消されない場合、原則として本件クーポン発行に用いるプラットフォーム上の機能を利用して出力されるクーポン利用履歴をもって、本件クーポン利用件数と扱うものとする。第X条(仕切価格の精算)
1. 販売元は、提供元に対し、対象顧客による本件クーポン利用件数に応じて、別紙クーポン条件書に定める「仕切価格」欄記載の金額を支払うものとする。
2. 甲は乙に対して、前条の照合結果に基づき、当該月分の仕切価格を、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3. 販売元及び提供元は、以下に定める場合には、当該クーポン利用分については精算対象外とすることを相互に確認する。
(1) 本件クーポンの利用が確認できない場合(無断キャンセル等によりクーポン利用済みとみなす場合を除く)
(2) 対象外サービスに本件クーポンが適用された場合
(3) 本件クーポンの内容や利用件数に関し不正または虚偽の事実が認められた場合
(4) その他、双方で別途合意された精算対象外の事由に該当する場合
別紙(クーポン条件書)記載例
クーポンの発行条件・方法や利用の際のルール、件数管理、仕切価格の精算など詳細な事項を別紙で決定する方式を採用した場合の別紙記載例を掲載しておきます。
実際の運用方針等に照らして、適宜アレンジの上ご活用ください。
| 対象サービス | ●●●体験60分コース(通常●●円) |
| 提供価格 | 無料 |
| キャンペーン期間 | ●年●月●日~●年●月●日 |
| 発行条件 | 上記期間中●件を発行上限とし、当該範囲内で販売元の裁量により発行可能とする。 発行上限枠の変更は、双方合意の上で実施する。 |
| 発行方法 | 販売元公式LINEのクーポン機能を利用する方法により発行 発行時、別途双方が合意した内容・方法により、注意事項(利用可能店舗、利用可能期間、利用方法、対象プラン等)の明示を行うものとする。 |
| 利用方法 | 提供元は、顧客からクーポンコードの提示を受け、クーポンが未使用の状態であることを確認し、「使用済み」処理を行ったうえでサービス提供を行うものとする。 |
| キャンセル | クーポン利用者が予約をキャンセルした場合、次の通り取扱うものとする。 (1) 前日までのキャンセルの場合:予約取消しまたは別日振替とする。 (2) 当日のキャンセルの場合:クーポン使用済とみなし、再使用は不可とする。 |
| 管理方法 | 発行件数の管理は販売元、利用件数及びキャンセル件数の管理は提供元が行い、双方月次で実績を共有する。 利用件数については、公式LINE機能における「使用済み」件数をもって照合を行う。 |
| 仕切価格 | 本件クーポン利用1件あたり●●●円(税別) |
| 支払期日等 | 支払期日、精算対象外事項等については、契約書第X条(仕切価格の精算)の定めに準じる。 |
その他(商標等の使用、契約終了時の措置)
提携に伴い、相手方の商標、ロゴ等を使用するケースも想定されます。その場合、利用範囲、期間や承諾の要否など、使用のルールを明確にしておく必要があります。
また、稀に、提携終了後もキャンペーンに関する告知や掲載等が残ってしまっているというケースがあります。この場合、顧客の誤認を招くおそれもありますので、表示・掲載の停止や商標・ロゴ使用の停止など、契約終了時の措置についても定めておくといざという時に安心です。
以下、商標等の使用や契約終了時の措置について、簡単な条項例をご紹介します。
第X条 (商標等の使用)
1. 販売元及び提供元は、本提携に関連して相手方の商標、ロゴその他のマーク(以下「本商標等」という。)を使用する場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。
2. 販売元及び提供元は、相手方の本商標等と同一又は類似の商標を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
3. 販売元及び提供元は、本契約が終了したときは、本商標等の使用を直ちに中止するとともに本商標等の表示を直ちに抹消又は削除しなければならない。第X条(契約終了時の措置)
1. 販売元及び提供元は、本契約の終了に際し、以下に定める事項を実施する。
(1) 本件クーポンの発行その他本提携に関連する施策を直ちに中止すること
(2) 本提携が終了したことを顧客その他関係者が判断できるように必要な表示・告知を実施すること
(3) 本件クーポンの有効期限その他本提携の終了に伴い必要な事項について、顧客その他関係者に対し適切な表示・告知を実施すること
2. 販売元及び提供元は、相手方が前項の措置を迅速に行わない場合、相手方に代わり、当該措置を講じることができる。
まとめ
「販売連携・クーポン施策型」の業務提携は、事業規模や業種を問わず実践可能なマーケティング手法であり、正しく設計すれば双方の利益につながる優れた連携モデルです。
しかしその反面、ユーザー対応や費用分担、知的財産、顧客トラブル対応など、曖昧なまま進めると後に大きな混乱を招くリスクもあります。
本記事で紹介したように、提携の設計段階から契約書における要点を整理し、関係者間で認識を共有しておくことが、安定したパートナーシップの鍵となります。
ぜひ、本記事の条項例を参考に、自社の提携スキームに応じた契約内容の検討に役立てていただければ幸いです。
また、本文中でも触れましたが、「業務提携」には他にも様々なスキームが考えられます。下記の関連記事で様々な提携スキームに関する解説記事を紹介していますので、合わせてご覧ください。
関連記事
- 本文中でも紹介しましたが、他の販売促進型の業務提携として、相手方の見込顧客を発見した場合に相手方に紹介・送客する「顧客紹介契約」や、相手方のサービスの販売権を授与してもらう「代理店契約」などがあります。これらについては↓の記事で詳しく解説しています。
- インフルエンサー等と提携して、商品・サービスのPRを依頼する「PR業務委託契約」については、↓の記事で詳しく解説しています。
- イベントや団体の活動を実施していく上で、資金提供や広告宣伝等を目的として企業と提携を行う「スポンサー契約」「協賛契約」については、↓の記事で詳しく解説しています。

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。