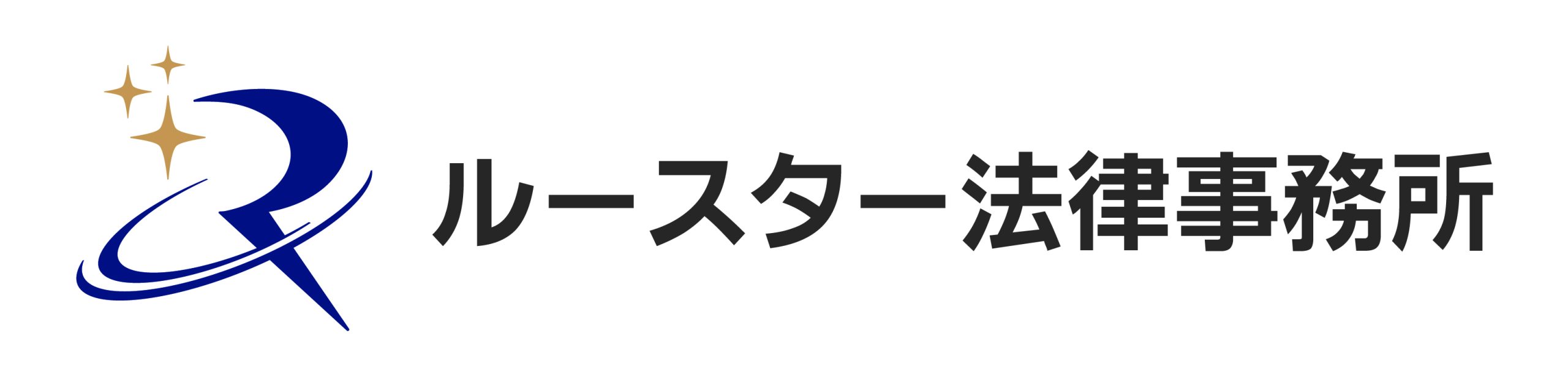「業務委託契約書」のポイントとひな型を解説
こんにちは。ルースター法律事務所 代表弁護士の山本です。
普段契約業務に関わっている方であれば、「業務委託契約書」というタイトルの契約を目にする機会は非常に多いのではないでしょうか?
業種にもよりますが、締結する契約書の中で業務委託契約書が最も多いという会社も少なくないでしょう。
特に、業務の効率化や事業の拡大を目的としてアウトソースを活用していく際、多くの場合は「業務委託契約書」を締結することになります。
アウトソーシングは現在も活発に行われており、今後もますます増えていくことが予想されます。
したがって、会社の規模の大小を問わず、業務委託契約書のポイントを理解しておくことは、事業をスムーズに進めていくうえで必要不可欠と言えるでしょう。
しかしながら、「いつもなんとなく業務委託契約書を締結しているが、今一つポイントがよくわからない」「契約書の内容と取引の実態が合致していないような気がする」など、業務委託契約書について疑問や不安に思う方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、「業務委託契約書」のポイントを解説していきたいと思います。
少し長い内容になりますが、業務委託契約書についてお悩みの方にはきっと役に立つ内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
業務委託契約書とは?
業務委託契約とは「仕事を依頼する契約」
「業務委託契約書ってよく目にするけど、実はイマイチよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?
実は、私も業務委託契約書についてポイントを解説しようと本記事を書き始めたのですが、これがなかなかに難しい作業でした。
その理由は、「業務委託契約」があまりにも多義的であるという点にあるのではないかと思います。
「業務委託」を一言でいえば、その名の通り「業務を委託する契約」です。
より平たく言えば、「仕事を依頼する契約」と言い換えることができます。
例えば、弊所の顧問サービスも、契約書作成、審査などの「仕事の依頼」を継続して受けるものですので、業務委託契約の一種に該当すると言えます。
システム開発やWEB制作、広告運用、人材紹介、代理店なども、一定の仕事を相手に依頼する契約と言えるので、もちろん業務委託です。
このほかにも、ベンチャー企業で実施されることが多い取引類型に絞っても、OEMなどの製造委託契約、BPOサービス、コンサルティング契約なども一定の仕事を相手方に依頼する契約であり、業務委託に該当しうることになります。
そう考えてみると、事業者間のあらゆる取引は、相手方に「仕事を依頼する取引」であり、「業務委託」に該当することになります。
逆に、「仕事の依頼」に該当しない取引を探す方が難しいと言っても過言ではないでしょう。
このように、「業務委託」という言葉自体が非常に多義的であり、企業間の様々な取引を包含する用語であるということを押さえておきましょう。
なぜ業務委託契約書はわかりにくいのか?
上記の通り、業務委託契約は非常に多義的な概念です。
そのため、上記で挙げたような「システム開発」「顧問契約」「人材紹介」のいずれも「業務委託」に該当すると言ってよく、すべて「業務委託契約書」というタイトルで契約書を作成してもまったく問題ありません。実際にそうなっている契約書も頻繁に目にするところです。
しかし、これらがいずれも同じ契約類型であり、必要な条項やポイントもまったく同じかと言われると、話が違ってきます。
なぜなら、それぞれの契約で依頼の対象となる「仕事の内容」が全く異なるものだからです。
そうであれば、仕事の性質・内容に応じて契約書上でポイントとなる部分も変わるはずだと考えるのが普通の感覚だと思います。
にもかかわらず、この点をあまり意識せず、「業務委託契約」と一括りにして説明されているケースがしばしば見受けられます。
結果、「システム開発」を想定して作成された業務委託契約書を「人材紹介」の取引において使用してしまうなどのケースが発生するわけです。
「業務委託契約書が取引の実態に合っていない」と感じたり、「この内容で問題ないのかイマイチよくわからない」と感じてしまうケースは、大抵これが原因です。
解像度を上げて考えることが重要
「業務委託契約」が事業者間のあらゆる取引を包含する概念であるため、一つにまとめて理解しようとすると非常にわかりにくくなってしまいます。
そればかりか、取引における重要なポイントを見逃してしまうことにもなりかねません。
例えば、「システム開発」の取引において、「紹介業務」を念頭に置いて作成された契約書を流用してしまったケースを考えてみましょう。
「システム開発」は、定められた納期までに、定められた仕様によるシステムを開発し、納品することを目的とする取引です。したがって、「納期遅延の場合はどうなるか」「納品されたシステムにバグや不具合があった場合はどうなるか」「完成前に契約が終了した場合はどう処理するか」などが重要なポイントになることは、契約書に詳しくない方でもなんとなく思いつくのではないでしょうか。
しかし、「紹介業務を念頭に置いて作成された業務委託契約書」には、このような状況に対応するための条項は通常規定されていません。そもそも紹介業務には、「成果物を作成して引き渡す」という前提自体が存在しないためです。
ところが、紹介業務を前提として作成された契約書だとしても、契約書のタイトルは「業務委託契約書」であり、内容もなんとなくそれっぽい内容に見えてしまうため、そのまま流用されることがままあります。
その結果、上記の重要なポイントへのケアが全くなされていない契約書が出来上がってしまうことになります。これでは、契約書を締結する意味がありません。
このような事態を防ぐためには、「業務委託契約書」と一括りに考えるのではなく、もう少し踏み込んで、解像度を上げて考えることが必要です。
つまり、契約書のタイトルが「業務委託契約」であっても、取引の内容が「システム開発」であるならば、「システム開発の契約書としてのポイントをクリアできているか?」という観点で考えなければ、効果的な契約書作成・審査を行うことはできないということです。
ただ、こればかりは、世の中にどういった類型の契約書ひな型があるのかを知っていなければ、考えようがありません。
そこで、「業務委託契約」と一括りにされることがある契約について、「この契約書類型に照らして考えた方がより適切」と考えられる例をいくつか挙げておきます。取引の目的・内容に合わせて、該当記事を参照するか、キーワードを変更して検索してみることをお勧めします。
- システム/アプリ等の開発・納品を目的とする取引 → システム開発委託契約書(記事公開予定)
- WEB制作/デザイン/コンテンツ制作を目的とする取引 → 制作委託契約書
- 商品の製造/OEMを目的とする取引 → 製造委託契約書・OEM契約書(記事公開予定)
- 人材紹介を目的とする取引 → 人材紹介契約書
- 顧客紹介/営業代行/代理店の依頼を目的とする取引 → 顧客紹介契約書・代理店契約書
- マーケティング/広告運用/集客代行の依頼を目的とする取引 → 広告運用委託契約書・ネット広告代理店契約書
- 専門分野に関するアドバイス/コンサルティングを目的とする取引 → コンサルティング契約書・顧問契約書
- イベント運営/キャスティングを目的とする取引 → イベント運営委託契約書
- 店舗運営業務の依頼を目的とする取引 → 店舗運営委託契約書
業務委託契約書を作成する上でのポイント
とは言いながらも、「業務委託」と呼称され得るあらゆる取引は、少なくとも「相手方に一定の仕事を依頼する契約」という意味では共通性を有しています。
したがって、契約書作成上どのようなポイントに注意すべきかについても、ある程度一般化することが可能です。
そこで以下では、「業務委託契約」において一般的に注意すべきポイントについて解説します。
あくまでも、「仕事を依頼する契約」に抽象化した範囲内での解説になりますので、より詳細な点は上記の目的・内容別の解説をご覧頂くか、専門家にご相談されることをお勧めします。
なお、仕事を依頼する側を「委託者」、依頼を受けて仕事をする側を「受託者」と言うのが一般的ですので、本記事でも同様に呼称します。
また、民法の請負契約に「仕事」という用語がありますが、本記事で用いる「仕事」という言葉は、民法上の定義からは切り離して、一般的な意味で「仕事」を指す言葉として使用していますので、その点はご了承ください(この説明が何を言っているのかわからないという方は読み飛ばしていただいて全く問題ありません)。
依頼する業務の内容と対価
業務委託契約書は「仕事を依頼する契約」である以上、「依頼される仕事の具体的な内容」と「その仕事に対する対価」に関する取り決めが最重要であることは言うまでもありません。
この点については、「どのような仕事を依頼するのか」の定義と、「どのような状態に至れば仕事の完了(対価の発生)と認められるか」の定義の2つの観点から検討することが重要です。
以下、それぞれにつき解説します。
「どのような仕事を依頼するのか」の定義
スポットの取引で、何をいつまでに行うかが明確に決まっているもの(「●月●日までにデザインを制作・納品する」など)であれば、仕事の具体的内容を定義することはさほど難しくありません。
しかし、継続的な取引で、仕事の内容自体が随時変更・調整されていくことを前提とする取引(コンサルティングなど)や、委託者からの依頼に応じて都度仕事が発生する取引(保守運用や顧問業務など)では、予め仕事の内容をすべて契約書に盛り込んでおいたり、仕事の依頼のたびに契約書を締結するというのは現実的ではありません。
したがって、具体的な仕事の依頼の方法や一般的な事項を「基本契約書」として締結した上で、具体的な業務内容、範囲、仕様、期間、委託料などの個別的な事項は別途発注書等により定めるとするのが最も合理的でしょう。
以下、コンサルティング業務委託における基本契約書の条項例を示しますので、参考にしてみてください。
第X条(業務の委託)
1.委託者は、●●●に関するコンサルティング等の業務(以下「本業務」という。)の遂行を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
2.受託者は、個別契約に定める内容に従い、委託業務を行うものとする。第X条(個別契約)
1.本業務の具体的内容、範囲、業務遂行方法、成果物の仕様等に関する事項、納期または委託期間、報酬その他の条件については、別途個別契約により定めるものとする。
2.個別契約は、委託者が指定する書式の注文書(電磁的方法を含む。以下同じ。)により発注し、受託者がこれを書面(電磁的方法を含む。)により承諾することによって成立する。
ちなみに、受託者側としては、あれもこれもと依頼されて本来の対応範囲を超えてしまうことがないように、依頼件数や対応時間の上限を定めるなどして委託料の範囲で対応する仕事の量を可能な限り明確にすることを目指したいところです。
例えば、発注書において次のような記載をしておくとよいでしょう。
発注書(個別契約書)記載例
委託者は、受託者に対し、業務委託基本契約書第X条の規定に基づき、以下の通り業務委託の発注を行う。
(1) 本業務の具体的内容・範囲
●●●業務(ただし、1ヶ月あたり●時間の対応時間を上限とする)
(2) 業務遂行方法
……
(3) 委託期間
20XX年X月X日から●ヶ月間
(4) 委託料
月額●円(ただし、受託者の対応時間が(1)に定める上限を超過した場合別途清算)
「どのような状態に至れば仕事の完了(対価発生)と認められるのか」の定義
多くの業務委託契約では、受託者が実施した仕事について、何かしらの方法により「仕事が完了したこと」を相互に確認したうえで、完了分について委託料を支払うという方式を取ることが一般的かと思われます。
したがって、いかなる方法、手続きによって仕事の完了を確認するかという点は、対価(委託料)の支払い条件にも密接に関係する事項であり、極めて重要なポイントです。
この点、WEB制作やコンテンツ制作において、受託者側としては制作作業が完了したと認識しているにもかかわらず、委託者側から「要求した内容を満たしていないから作業が完了していない」として、代金支払いを拒否されて困っている……というケースをよく目にしますが、この手のトラブルは、仕事に要求される水準や満たすべき条件と、その仕事の完了の確認プロセスが曖昧になっているのが原因であることが大半です。
契約書上では、「仕事に要求される水準や満たすべき条件」を「仕様」などと呼び、「仕事を完了したことの確認プロセス」を「納品・検収」などと呼んでいます。
上記の制作委託契約やシステム開発契約、商品の製造委託契約のように、「成果物を納品すること」を目的とする取引であれば、仕事の完了の確認プロセスは、「納品された成果物が定められた仕様を満たすかをチェックする作業」になります。
具体的には、次のような条項です。
第X条(仕様等)
受託者は、別途協議の上で決定する仕様等に従い成果物を作成し、又は委託業務を遂行するものとする。第X条(納品・検収)
1. 受託者は、個別契約にて定める納期、納入場所及び納入方法に従い、成果物を納入するものとする。
2. 委託者は、成果物の納入を受けた後●●日以内(以下「検査期間」という。)に、別途協議の上定める検査基準に従い検査を行うものとし、検査に合格したときは、受託者に対して書面により(電磁的方法による場合を含む。)検査合格の通知を行い、これをもって検収完了とする。
3. 検査の結果、成果物が不合格となった場合又は委託業務が適正に遂行されていないことが判明した場合、委託者は、受託者に対して遅滞なくその旨を通知するものとする。
4. 前項の場合、受託者は、別途委託者が定める期間内に、自己の費用と責任において不合格の原因となった種類・品質・数量に関する契約内容の不適合その他不具合等を無償で補修又は代替品を納入し、又は業務の追完を行った上で再度検査を受けるものとし、以後同様とする。
5. 検査期間内に、第3項の不合格通知が交付されなかった場合には、検査期間の経過をもって、成果物は検査に合格し又は委託業務が適正に遂行され完了したものとみなす(※)。第X条(委託料)
委託者は、受託者に対し、成果物の検収完了の日が属する月の翌月末(当該期限の末日が金融機関の休業日にあたる場合、その前営業日)までに、委託料として金●●万円(税別)を、受託者が別途指定した銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は委託者の負担とする。
※を付した条項は「みなし合格条項」などと呼ばれ、検査期間内に異議を述べなければ検査に合格=仕事が完了したものとして扱う、というものです。
この条項があると、仕事が完了したことを容易に証明することができる可能性が高くなるため、受託者側としてはぜひ入れておきたい条項です。
他方、成果物の納品を目的としない取引(作業の依頼などを目的とする取引)の場合、「業務完了報告書」等の方法により仕事の完了を確認するという条項が設けられているケースが多いと思われます。
その場合、上記の条項の「成果物を納入」を「業務完了報告書を提出」に置き換えればOKです。
なお、成果物や業務が満たすべき水準・条件=「仕様」については、取引ごとに、委託者の要望や予算などに応じて決定されることが通常と思われます。
どのラインをクリアすれば仕事が完了したことになるのかを決める作業であり、可能な限り具体的かつ明確に定めておくべきであることは言うまでもありません。
契約締結時に決定している事項があれば、別紙に箇条書きで列挙する程度でもよいので明示しておきましょう。
契約締結段階では未定の場合は、可能なら仕様書や覚書、あるいはミーティング議事録、最悪メールやチャットのやり取りでもよいので、仕様に関して決定事項が生じたら必ず記録に残る形で合意を取っておくことが必要です。
いずれの方法を取るにせよ、大事なのは、後日仕事が完了したか否かを巡ってトラブルになった際に、「合意していた仕事の水準・条件はこういう内容で、当方の仕事はこれらを満たしています」ということを、客観的な根拠をもって言える状態にしておくことです。
これがあるのとないのとでは、代金を回収できるか否か、交渉を有利に進められるか否かが180度違ってきます。
このように、「仕事が満たすべき水準・条件」と「仕事の完了の確認プロセス」を明確に定義することが業務委託契約を円滑に進めるうえで最重要のポイントになりますので、慎重に検討しましょう。
権利の帰属
特に成果物を納品する取引においては、成果物の権利がどちらに帰属するのかを巡ってトラブルに発展することがあります。
例えば、あるSNS広告に出稿するという前提で、広告デザインの制作を依頼したとしましょう。
デザインの納品・検収完了後、委託者が当初予定されていた媒体に出稿するにあたっては、おそらく何の問題も生じないでしょう。
しかし、同じデザインを自社HPやLPにも流用したいと考えた場合はどうでしょうか?
この点、もしデザインに対する権利(著作権)が受託者側に残っているのであれば、たとえ委託者といえども、権利者である受託者の承諾がない限り無断でデザインを流用することはできません。
しかし、委託者としては、成果物を今後自由に利用可能であることを前提に委託料を支払うと認識しているのが通常であると思われます。
したがって、成果物に関する権利(著作権)が受託者から委託者に移転することを明確に規定しておく必要があります。
また、成果物の扱いとは別に、仕事の遂行過程上で知的財産権の帰属が問題となるケースも多々あります。
例えば、アパレル業者とOEM契約を締結して新規ブランドを立ち上げるケースを想定してみましょう。
この場合、新規ブランドに関して生じる権利(商標権など)はどちらの所有になるでしょうか?
この点、受託者側(上記事例でいうとアパレル業者側)が、委託者に断りなくブランド名を商標出願していたことが後から判明するというようなケースが結構あります。
このようなケースでは、契約解消後に委託者が同一ブランドを継続しようとする場合、受託者が取得した商標権を買い取るなどの対応が必要となる可能性があります。
このようなトラブルを防ぐために、仕事の遂行の過程で生じる権利の帰属も定めておく必要があります。
以下は、これらの権利が委託者側に帰属すると定める場合の条項例です。
もっとも、権利の帰属は、両者の利害が対立する場面でもあり、委託料など他の契約条件にも影響しうる問題であるため、慎重に検討の上、相手方とも十分に協議して決定しましょう。
第X条(成果物に関する権利)
1. 成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、全て委託者に帰属するものとし、権利の発生と同時に委託者に移転するものとする。なお、受託者から委託者に移転する著作権の対価は、委託者が受託者に支払う委託料に含まれるものとする。
2. 受託者は、委託者及び委託者の指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。第X条(知的財産権等の取扱い)
1. 委託業務遂行の過程において生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等にかかる知的財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいい、以下、これらの権利を総称して「知的財産権等」という。)は、全て委託者に帰属するものとする。
2. 受託者は、委託業務遂行の過程において知的財産権等が発生した場合、委託者にこれを通知しなければならない。
委託者による協力義務
受託者側にとって重要となる場面が多い規定として、「協力義務」が挙げられます。
依頼された仕事を遂行するにあたって、委託者からの協力を得なければならない場面が出てくる可能性があります。
例えばコンサルティング契約では、受託者がより効果的な助言、提案を実施するためには、委託者からの資料提出やミーティングなどへの協力をしてもらう必要があるでしょう。
また、受託者が提案、助言した施策を、委託者に誠実に実行してもらうことも必要です。
委託者がこのような必要な協力を行わなかったために仕事が進まなかったにもかかわらず、それを理由に報酬支払いを拒絶されたのではたまったものではありません。
このようなトラブルを防止するためには、委託者側に協力義務があることを明確に定めることが有効です。
具体的には次のような条項になります。
第X条(協力義務)
1. 受託者は、委託者に対し、委託業務の遂行に際し必要な協力を要請することができるものとし、委託者は受託者から協力を要請された場合には遅滞なくこれに応ずるものとする。
2. 委託者が前項に定める協力義務に違反し、受託者に損害が生じた場合、委託者は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。またこの場合、受託者は委託者の協力なしには遂行困難な委託業務に関する責任を免れるものとする。
再委託
受託者が、引き受けた仕事をさらに第三者に依頼したり、第三者に仕事の一部を手伝ってもらいたいという場面も想定されます。
これは、契約書上で「再委託」と呼ばれるケースです。
受託者としては、一般的には、自己の判断により自由に第三者を関与させられる方が便利であると言えます。
しかし、委託者としては、受託者との信頼関係や業務遂行能力に基づき仕事を依頼している場合等、あまり第三者が関与することが好ましくないケースも少なくないでしょう。特に、個人情報や機密情報の取扱いが生じる業務であれば、これらの情報があずかり知らない第三者にわたってしまうことは極力避けなければなりません。
そこで、再委託に関するルールが必要となります。
一般的には以下の条項例の通り、再委託は事前承諾が必要であり、かつ再委託先の行為につき受託者が連帯して責任を負うという取り決めがなされることが多いように思われます。
第X条(再委託)
受託者は、書面により事前に委託者の承諾を得た場合に限り、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。この場合、受託者は、再委託先に対して、本契約及び個別契約において受託者が負う義務と同等の義務を負わせ、当該再委託先の行為について連帯して責任を負うものとする。
もっとも、これが絶対的なルールというわけではありません。
業種や仕事の内容によっては、そもそも第三者が関与することが当然の前提となっている場合もあり、毎回事前承諾が必要としたのではかえってスムーズな取引遂行の障害となってしまうケースもあり得ます。
このようなケースでは、再委託先に関する情報を提供する義務にとどめるなどの調整をすることも考えられます。
仕事の内容、背景事情や再委託先が関与することによるリスク等を勘案して、適切な条件を設定しましょう。
契約終了
業務委託契約では、契約の終了を巡ってトラブルになるケースが後を絶ちません。
例えば、システム開発など成果物の制作を目的とする取引においては、どちらかの当事者が成果物の完成前に契約を終了させようとする場合に激しいトラブルになりがちです。委託者としては、成果物が完成していない以上代金は支払いたくないと考えるのが通常である反面、受託者としては途中までとはいえ実際に作業負担が発生している以上、一定の費用は負担してもらわなければ困ると考えるためです。ここに、上記でも述べたような「成果物が要求された水準を満たしているのか問題」が絡んでくると、もはや当事者間での解決は不可能なレベルの紛争に至ってしまうことも珍しくありません。
また、継続的に仕事の受発注を行う取引においては、お互いに今後も取引関係が継続することを前提として予算や人員配置を組んだり、必要な投資を行うことが通常です。したがって、突然契約を打ち切られてしまうと、大きな損害を被ったり、投下した資本の回収が不可能になってしまうなどの問題が生じることになるため、やはり契約終了を巡って激しいトラブルになるケースが非常に多いと言えます。
一方的に契約を終了させることはある意味究極的な場面であるため、トラブルが発生してしまうリスクをゼロにすることは不可能です。
しかし、様々な事情から、一度開始した業務委託契約関係を打ち切らなければならない場面が出てきてしまうこともまた避けられません。
したがって、可能な限り、契約終了に関するトラブルのリスクを抑え、トラブルが発生した場合も有利かつ円滑に解決することができるようにしておくことが重要なのは言うまでもありません。
契約終了については、「どのような場合に契約を終了させることができるか」と「契約終了後の処理はどうするか」の2つの観点から条項を検討することが重要です。
以下、それぞれにつき解説します。
「どのような場合に契約を終了させることができるか」の定義
前提として、予め契約の有効期間を定めておき、その期間が満了したことをもって契約終了とするというのが、平常時における契約終了の方法となります。
もっとも、有効期間満了のたびに契約書をまき直すというのも不便であるため、期間満了に際して当事者から特に申し出がなければ契約がそのまま更新される(自動更新)という方式を採用している契約書も非常に頻繁に見受けられます。以下に示す条項例もこのような方式を採用しています。
この場合、定められた期間内に「契約を更新しない」旨を通知すること(更新拒絶)によって契約を終了させることになりますので、その点は注意が必要です。
むしろ、契約が更新されない方が都合が良いのであれば、以下の条項の「ただし~」以下は削除した方が良いでしょう。
第X条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までに契約当事者のいずれかから別段の申出がないときは、自動的に同条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
これに対し、仕事の継続中や契約期間内に契約を終了させたいと考える場面としては、主に次の2パターンが想定されます。
- 相手方による契約違反や信用不安などが生じた場合(納期遅延、代金支払いの不履行、倒産など)
- 自社都合による場合(プロジェクトの中止や予算不足、代替先の確保など)
契約書上、①のように、相手方に一定の事項が生じたことを理由に契約を終了させることを「契約解除」、②のように、相手方に生じた事項とは関係なく、自己の都合により契約を終了させることを「中途解約」と使い分けていることが多いように思います。
①については、一般的には次のような条項が設定されることが多いと思われます。
下記の第1項と第2項に列挙された事由(解除事由)が、「どのような場合に契約を終了させることができるか」の定義の部分に当てはまります。
基本的にはこのような条項で事足りると思われますが、このほかに契約を終了させるべき事態が想定される場合には解除事由として明記しておく必要があります(例えば、タレントやインフルエンサー等との契約においては、タレントによる違法行為や不祥事が発覚した場合などを解除事由として設定しておくケースがよく見られます)。
第X条(解除)
1. 委託者及び受託者は、相手方が本契約又は個別契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2. 委託者及び受託者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)営業の許可取消し又は停止等があったとき
(2)支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5)租税公課の滞納処分を受けたとき
(6)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9)本契約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10)その他、本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
(11)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
3. 前二項による解除は、委託者又は受託者の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
4. 委託者又は受託者が第2項各号の一に該当する場合、当該当事者は、何らの催告なしに、自己の債務について直ちに期限の利益を喪失するものとする。
これに加えて、②のように、相手方に生じた事項とは関係なく、自己の都合により契約を終了させたいと考える場面も想定されます(中途解約)。
中途解約を可能とするためには、契約書上、以下のような条項を設定しておく必要があります。
第X条(中途解約)
委託者及び受託者は、1か月前までに相手方に対し書面をもって通知することにより、本契約又は個別契約を中途解約することができるものとする。
中途解約条項は内容もシンプルで一見目立たない条項であり、何気なく契約書に入っていることも多いです。しかし、その内容は、何の理由もなく任意に契約を終了させることを可能とするものであり、極めて取引への影響度が高い規定です。
特に継続的な受発注を行う契約においては、何の理由もなく中途解約を行うことは相手方に対して大きな損害を与えることになるため、当然に認められる権利ではありません。最低限、契約書上に明記がなければ、中途解約を行うことはできないと考えておいた方が良いでしょう。
したがって、中途解約の可能性が想定されるのであれば、必ず契約書上に明記しておくべきと言えます。加えて、「中途解約による損害を賠償する責任を負わない」との条項を入れておけばより有利にはなりますが、あまりに一方的な条項であるとして契約交渉時に相手方に不信感を与えるおそれもありますので、慎重に検討しましょう。
逆に、中途解約されるリスクの方が大きいと考えるのであれば、本来当然に認められるような権利ではありませんので、中途解約条項自体を削除すべきです。それが難しくても、少なくとも解約予告期間を長くしたり、解約による損害を賠償する責任を負うとの条項(例えば「委託料の●ヶ月分を補填する」など)を入れるなどの調整は試みるべきでしょう。
「契約終了後の処理はどうするか」の定義
契約が終了した場合にどうなるかも非常に重要な問題です。
むしろ、契約終了に伴うトラブルは、「終わること自体は致し方ないが、終了に伴う問題の処理が折り合わない」というのが実態であることがほとんどです。
その意味では契約終了のトラブルの本質的な要因は、「契約終了後の処理」にあると言ってもいいかもしれません。
具体的には、作業途中の成果物や進行中の業務の取扱いとそれに対する対価の問題、貸与した資料・データや使用を許諾している商標などの取扱いが問題となります。
以下、契約終了時の措置を定める一般的な条項例を記載しておきます。
実際の契約締結に際しては、契約終了に伴いどのような問題が生じ得るか、それをどのように解決することが望ましいかを慎重に検討し、相手方とも協議の上で契約条項に落とし込むようにしてください。
第X条(契約終了時の措置)
1. 本契約の終了時に有効な個別契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該個別契約の遂行についてなお本契約が適用されるものとする。
2. 受託者は、本契約が終了した場合、委託者の指示に従って以下の措置を執った上で、委託者に対して書面で報告する義務を負う。
(1) 委託者が貸与した資料、貸与品または秘密情報が記載された一切の文書・データ等を委託者の指示に従って返還または廃棄すること
(2) 本契約に基づき使用を許諾された商標等の使用を速やかに停止すること
(3) ……第X条(中途成果物の取扱い)
1. 本契約又は個別契約が期間途中で終了した場合、委託者が要求する場合には、受託者は委託者に対し、中途成果物を引渡すものとする。
2. 前項の場合、委託者は受託者に対し、中途成果物の対価を支払うものとする。その際の中途成果物の対価は、委託業務遂行に受託者が要した費用、工数等に基づき、委託者が合理的に算定した金額とする。第X条(引継ぎ業務)
受託者は、委託者が希望する場合、委託者又は委託者が指定する第三者に対して、委託業務と同等の業務を行うために必要となる引き継ぎ業務を無償で行うものとする。
まとめ
以上、業務委託契約書のポイントを解説しました。
繰り返しになりますが、「業務委託契約」は非常に多義的な用語であるため、契約書のタイトルなど表面的な部分ではなく、より踏み込んで取引の目的や内容に照らし合わせて条項を検討していくことが重要です。
そして、スムーズに取引を進めていくためにも、契約書をしっかりと作成しておくことは決して軽視してよい工程ではないことが少しでも伝わっていれば幸いです。

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。